Spotify、過去1年で7,500万曲以上の「スパム的な楽曲」削除 新たなAI音楽ポリシー発表

Spotifyは9月25日、AI生成コンテンツの管理に向けた一連の新方針を発表。過去1年間に7,500万曲以上の「スパム的な楽曲」を削除したことを明らかにした。併せて「業界にはAIの透明性に対する繊細なアプローチが必要であり、全ての楽曲を『AIか否か』で二分類することを強制されるべきではない」との見方を示した。
<重点的に取り組む分野>
①なりすましの取り締まり強化
不正なAI音声クローンおよびあらゆる形態の音声複製やなりすましを禁止する、新たな「なりすまし対策ポリシー」を導入。模倣対象アーティストが使用を許可した場合に限り、声の模倣を認める。
不正行為者が他アーティストのプロフィールに音楽をアップロードする「コンテンツミスマッチ」は、ディストリビューターと連携し、攻撃を根源から阻止する対策を試験中。
②新スパムフィルタリングシステム
AIを活用したコンテンツ操作を検知するスパムフィルターを段階的に導入。不正が検知されたコンテンツは、Spotifyのあらゆるプログラムでレコメンデーションが停止される。
③業界標準クレジットに基づくAI開示
DDEX(デジタルデータエクスチェンジ)を通じて開発された音楽クレジットにおけるAI開示の新たな業界標準の構築を支援。アーティストらは、AI生成ボーカル、楽器演奏など、AIが制作にどこでどう関与したかを明確に示せるようになる。パートナー企業を通じて情報が提供され次第、アプリ全体で表示を開始する。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「SpotifyがAI生成曲に関する新たなポリシーを発表。合わせて過去1年に7500万曲以上のスパム楽曲を削除してきたと公表した。365日で割ると1日20万曲以上に当たる。AIによるストリーミング詐欺の被害額は3500億円前後と日本の音楽ソフト売上を超える規模になっている。Spotifyは既に一曲すべてを丸々AIで生成した曲を削除しており、それはAIバンド騒動を起こしたVelvet Sundownの新アルバムが全て削除されたことでも確認されているが、今回の新ポリシーでは新スパム・フィルターの他に、「アーティストの許諾を得てない」音声クローンの削除、AIを楽器演奏やコーラスパートなど曲の一部に利用した場合に明示する新しいクレジット表示が採用された。アーティストの許諾を得た音声クローンの例は、私が新潮の連載で「音楽と生成型AIの現在地」のオアシス、「音楽家がAIに転生するとき」のグライムスを取り上げているのでお読みいただければ幸いだ」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
- Spotify公式
- DMN:Is Streaming’s ‘AI Slop’ Problem Even Worse Than We Thought? Spotify Bolsters ‘AI Protections for Artists,’ Says It’s Booted ‘Over 75 Million Spammy Tracks’ During the Past Year
- MBW:Spotify has deleted 75m+ ‘spammy tracks’ – as it unveils new AI music policies
- Deezer、1日3万曲のAI生成音楽がアップロード 全体の28%に拡大
- Spotifyがお騒がせAIバンド「The Velvet Sundown」の複数曲削除 英国レコード産業協会、AI楽曲タグ付けの必要性を訴え
- 「AIがストリーミング再生回数を奪っている」中南米のミュージシャンら訴え
- インディーズが詐欺師の標的に 本物のミュージシャン名義でAI音楽がリリース
- ストリーミング詐欺で年4500億円超の損失か 詐欺撲滅へBeatdappが提携拡大
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
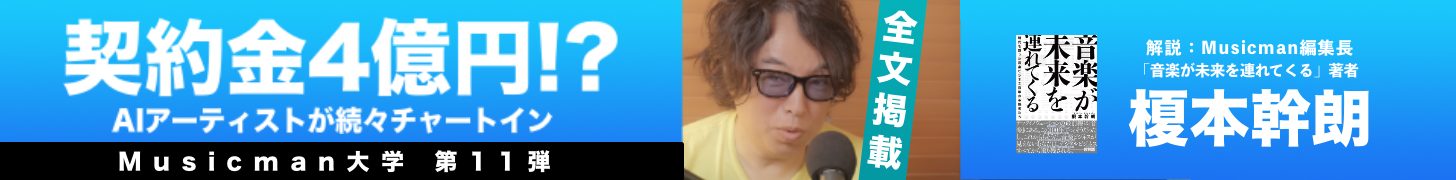
広告・取材掲載