【全文掲載】早く対応しなきゃ稼げない!?Z世代とα世代の音楽体験に相違が…Spotify ロスレス音質提供開始!【榎本編集長のMusicman大学#9】

MC Tama: 榎本さん、今日のテーマは何ですか?
榎本: 「Spotify待望のロスレス音質の提供開始」という記事がバズったので、この話をします。
MC Tama: どうなったんですか?
榎本: 要するにCDと同じ音質になりました。9月10日頃からApple MusicとAmazon Musicはロスレスでしたし、ハイレゾでCDよりも良い音で聴けました。しかし、今までSpotifyでは聴けませんでした。

MC Tama: そうなんですね。
榎本: レコード会社からOKが出たのですが、その理由は、SpotifyがMusic Proという通常価格の1.6倍の豪華プランを始めるからです。基本無料プラス有料という形だと、どうしてもアーティストやレコード会社に支払う1回再生あたりの金額が下がってしまいます。そうすると、そんなに低いギャラでは許可を出したくないという雰囲気でした。しかし、1.6倍のVIPプランを作ってくれるなら、やってもいいという話になったようです。
ロスレス音源はMusic Proで最初にやる予定でしたが、いきなり通常プランでロスレスになったので、音楽業界の人も驚きましたし、一般の音楽ファンの皆さんもようやくSpotifyがロスレスになったと喜んでいます。
MC Tama: Spotifyの無料版に大きな変更があったと聞いたのですが。
榎本: 今までこの曲を聴きたいと思ってポチッと押しても再生されず、プレイリストの何かの曲がシャッフルで再生されていました。それが嫌なら有料化する必要がありました。しかし、無料版でもYouTubeのように、この曲を聴きたいと思ってポチッと押したら再生されるようになりました。
MC Tama: 良いことづくめですね。
榎本: そうですね。無料版ではオンデマンドになり、有料版ではロスレスになり、ユーザーの皆さんは嬉しいのではないかと思います。しかし、音楽業界にとってはいろいろと課題があり、Spotifyが気がついてこういう風にやらせてくださいという話になっているのです。
MC Tama: なぜ困るのですか?
榎本: もともとSpotifyには無料版があって、そこから有料になってもらうというモデルでした。無料版はシャッフルでオンデマンドではなく、好きな曲をすぐ聴けませんでした。有料だとそれができるという形にしていました。しかし、これが若い子たちに通用しなくなってきたのです。
若い子たちはYouTubeやTikTokで音楽を聴いているのです。YouTubeは当たり前ですが、この音楽ビデオを聴きたいと思ってポチッと触ったら再生されます。それに慣れているのです。TikTokはスワイプしたら、いい感じで好きな曲みたいなのが流れてきます。それに慣れているので、Spotifyが無料版はシャッフルですとなっていると、使ってくれなくなってしまったわけです。
YouTubeにはYouTube Musicがあるので、広告なしで音楽を便利に楽しみたいなら、YouTube Musicと同じような形にSpotifyもしないと戦っていけません。使ってもらえないということが起こっているのです。
話を整理すると、Spotifyの無料プランはオンデマンドでYouTubeと同じにしました。有料にするとロスレスで良い音になり、広告はつきません。さらに上のプランのMusic Proだと、チケット先行やハイレゾなどがつくようになります。ようやく他の媒体と同じような感じになってきたという状況です。
MC Tama: そうせざるを得なかったのですね。今回はユーザーへの利益還元として行われているということではないのですか?
榎本: 違います。むしろ危機感を持っているのです。Spotifyとレコード会社の両方が危機感を持っています。Z世代の中でも10歳から29歳という幅広い層がいますが、特にZ世代の若い世代はYouTubeとTikTokを使って終わり、サブスクまでいかないのです。
MC Tama: よく榎本さんが言う受動的なということですね。
榎本: そうです。まずYouTubeで音楽ビデオが勝手に次のものも再生されます。アルゴリズムによってです。TikTokもスワイプしていたら、勝手に好きそうな動画がどんどん来ます。これもアルゴリズムですが、それで満足してしまうのです。自分から音楽を掘っていきたい、この曲をこのアーティストをどんどん深掘りしたいという、こういう能動的な聴き方をしないのです。世代的にアルゴリズムに慣れているのです。YouTubeやTikTokのアルゴリズムに。
音楽業界もSpotifyも、YouTubeやTikTokしか使わない子たちにどうやったらサブスクまでたどり着いてもらうかを考えて話し合って、YouTubeと同じにしたのです。簡単に言うと、無料で好きな曲をオンデマンドでポチポチと押したら聴けます。ただし、広告がつきます。有料会員になったら広告が外れるし音も良くなる。そういうふうにZ世代の若い世代に適応したサービスを提供しようということになったのです。
これは大きな変化です。今まで特に2000年以降はインターネットでコンテンツを買わなくなりました。CDを買わなくなった。あるいはDVDを買わなくなりました。代わりに2つ出てきたのです。モノ消費ではなくコト消費、体験にお金を使う。CDは買わないけど、ライブにはお金を使うということです。あるいは利便性です。便利なものだったらお金を払う。聴き放題とか動画の見放題だったらお金を払うとなっていました。
しかし、コト消費というのは能動的なのです。だけど新しい世代はアルゴリズムに慣れていて、おすすめされるアルゴリズムは裏でAIを使っているので、AI世代になるのです。この子たちはいつもおすすめされているので受動的なのです。そういう子たちに能動的になってもらうというのが新しいテーマになるわけです。音楽業界全体のテーマです。
そういう子たちが受動的な中で、能動的なことをやるのが楽しいという流れを作っていかないといけないので、それをどうやって作っていくかが新しい課題になるのです。

今までだったら物を買わない代わりに体験しに行く、この前提は能動的でした。ライブを体験しに行くというのは相当ハードルが高いです。ライブはわざわざチケットを買って、おしゃれして友達を誘って行くという、相当ハードルが高く、相当エネルギーが必要なのです。そういうのが楽しいということを、このスマホネイティブ、あるいはアルゴリズムに慣れてしまっている子たちにどうやって伝えていくか。その動線をこれから作っていかなければいけないのです。
ただ、これはZ世代より上の世代の人たちにはあった習慣なのです。例えばテレビで音楽を聴く、ラジオで音楽を聴く、それで終わり。こういう人たちの方が多数派でした。その一部の人がCDを買って、その一部の人がライブに行くというのが、Z世代より上のミレニアル世代、それよりもさらに上の私たちの世代、ジェネレーションX、今の40から50代にとっては普通でした。
MC Tama: その世代に少し戻りかけているのですね。
榎本: そうです。面白いのが、今の10歳とか15歳ぐらいのローティーン層で起こっていることが、名曲や名作が好きだということです。今の子たちは何でも聴き放題で、耳に入ってくるので、今日聴いた良い曲が新曲なのです。リリースしたタイミングではなく、自分が初めて良いなと思った瞬間が新曲なのです。
MC Tama: その感覚分かります。ジェネレーションXの世代の私は、例えばCMを見ていてアップルがCMの曲でローリング・ストーンズの「She’s a Rainbow」がかかった時に、何だこれはと思ってすごく探したり、どのアルバムなのだろうとか、そんな感じの感覚と一緒ですね。

榎本: そうです。それが上の世代よりも強いのです。やはり聴き放題が普及したので、実際にその聴き放題の6割以上がいわゆるカタログ曲、昔の曲の方が聴かれているのです。新曲は少数派になっているのです。そういう名曲や名作が好きだというのが一つです。
あと、アルファ世代はコレクションが好きです。親の影響もあるのですが、何だかんだ形で好きなものはコレクションとして持ちたいのです。今はCDかレコードしかないので、どちらかを買うしかないのですが、本当は彼らは何か新しいものが欲しいでしょうね。CDやレコード以外が何かできれば少し変わってくるかなという感じがします。
話をまとめると、アルファ世代あるいはZ世代の下の世代はアルゴリズム世代で、おすすめに慣れているので受動的で能動的ではなく、コト消費、体験を求めに行かなくなっているので、そこは新しく対応していかなければいけません。音楽業界もIT業界も対応が必要です。
もう一つが、今言ったように名曲や名作が昔よりも受けるようになっているので、それを若い子たちに伝えていく形を作っていかなければいけません。実際にTikTokなどで昔の曲がいきなりバズるということがしょっちゅう今起こっているので、そういうのが新しいプロモーションで必要になってきます。カタログをプロモーションしていくということが昔よりも必要になってきます。
あともう一つが、その所有欲、コレクションというのも新しいデジタルネイティブ世代が求め始めているので、それに対応する何かを作らないといけません。CDに代わるコレクションです。
これが3つです。今まではSpotifyのサブスク聴き放題、あるいはそういうAIでのアルゴリズムでのおすすめで聴くというのが最先端の世界でしたが、アルファ世代はもっと先のものを求め始めています。だから、これから新しいものが出てくるでしょうという話でした。
音楽に受動的なアルゴリズム世代に、いかに音楽を能動的に楽しんでもらうか。世界の事例を見るといくつか答えが出ているので次回以降お話させていただきます。
MC Tama:ありがとうございました。
プロフィール
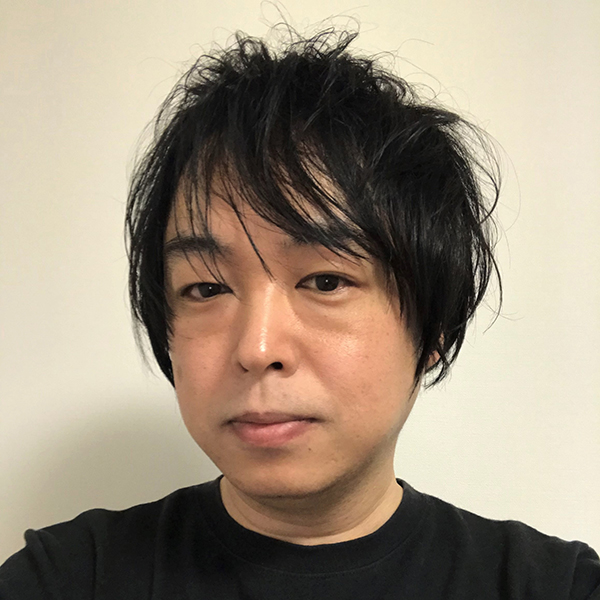
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。Musicman編集長・作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。著書に「音楽が未来を連れてくる」「THE NEXT BIG THING スティーブ・ジョブズと日本の環太平洋創作戦記」(DU BOOKS)。『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載。
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載