Spotify、ディスカバリーモードのペイオラ疑惑で集団訴訟に直面

Spotifyは、「ディスカバリーモード(パーソナライズプレイリストに楽曲をプッシュ)」がレコード会社やアーティストが宣伝のために金銭を支払う「ペイオラ」の一形態に過ぎないと主張する集団訴訟に直面している。ニューヨークの連邦地方裁判所で11月5日に提起された訴訟には、ユーザー約100人が参加。賠償金500万ドル(約7億7,000万円)以上を請求している。
原告側は、Spotifyが「オーガニックな音楽レコメンデーションを提供するプラットフォームとして自らを売り込むことでユーザーの信頼を悪用し、その推薦枠を密かに最高値の入札者に売り渡している」と主張。ディスカバリーモードの正確な性質をユーザーに開示していないと指摘した。
これについて、Spotifyは「全くのデタラメだ」と反論。ディスカバリーモードが影響するのはラジオ、自動再生、特定のミックスのみで、訴訟で言及されているDiscover WeeklyやAI DJといった主力プレイリストには影響しないと説明した。
ディスカバリーモードは2020年の導入当初から批判に直面しており、ラジオ局に放送料を密かに支払う「ペイオラ」と類似しているとして、米議会の調査対象となったこともある。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「Spotifyが賄賂(ペイオラという)をもらってディスカバリーモードを操作していたという集団訴訟がアメリカであった。Spotify側は「全くのデタラメ」と反論。Spotifyにはバナーや音声広告が用意されており、もちろんそこはペイオラ(賄賂)には相当しない。ディスカバリーモードはアルゴリズムで自動的に曲をかけていく機能で、原告はSpotifyがこのアルゴリズムを賄賂でいじったと訴えている。常識的には上場企業であるSpotifyが違法なペイオラで稼ぐことは考えにくい。メインのサブスク売上と比べてわずかな金額にしかならず、その程度のために法を犯すのはリスクが大きすぎるからだ。ペイオラというのはラジオDJがレーベルなどからお金をとって音楽をおすすめすることで、「紹介トークをして曲をかける」という今では常識となったラジオDJのフォーマットを発明したアラン・フリードが「レーベルの宣伝マンから金銭を受け取っている」という批判を受け、これを禁止する法律がアメリカで出来た。その結果、宣伝費をもらって楽曲をかける場合はリスナーにちゃんとそれが「宣伝だ」と伝わるようにしなければいけなくなっている(Spotifyならバナーや音声広告)。どのような根拠を見つけて訴えているのか、今後を見守りたい」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
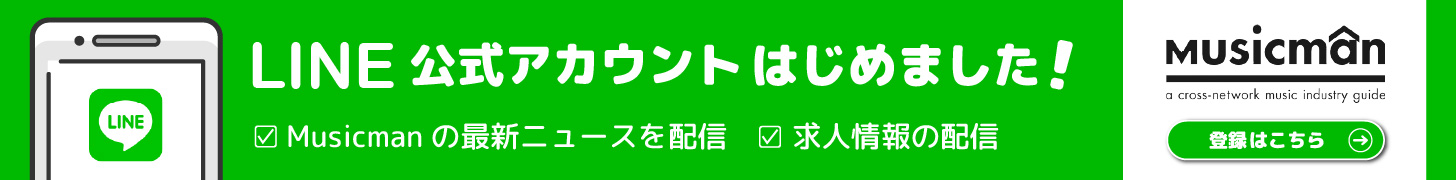
広告・取材掲載