「AIがストリーミング再生回数を奪っている」中南米のミュージシャンら訴え
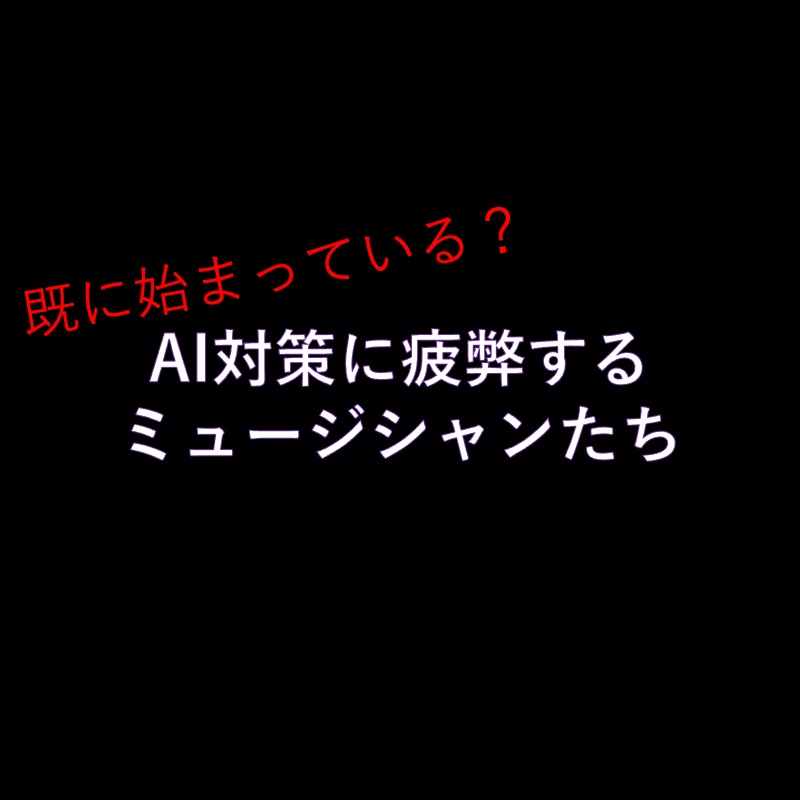
AI生成楽曲がストリーミングプラットフォームを席巻している中、中南米のミュージシャンらが、ボットがストリーミングの再生回数を盗み、収入を吸い上げ、楽曲の寿命を縮めていると訴えている。欧米諸国以外のテクノロジー関連ニュースを扱う米国の非営利メディア「Rest of World」が9月9日伝えた。
ラテン音楽業界の関係者によると、AI音楽リリースの速度と量は、今や人間のアーティストを疲れさせ、リスナーの注意を散漫にさせているという。
楽曲制作の代わりにプロモーションに創造性と労力を注ぐことを強いられ、それを実行しても、リスナーはすぐに興味を失い、ストリーミングプラットフォームからの分配もごくわずかにとどまる。中南米でも再生回数が会場ブッキングや公的資金獲得などの指標となっているため、ストリーミングプラットフォームを離れるのは、大半のアーティストにとって現実的ではない。
過去には、バッド・バニーの声を複製して作成された楽曲が、チリのSpotifyで一時トップ100入りを果たし、その後プラットフォームから削除される事態も起きていた。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「生成AIの楽曲がディストリビューターなどを通じて大量にアップされボットで自動再生されている問題で「ミュージシャンの収入を吸い上げ楽曲の寿命を縮めている」という声が上がった。中南米はAIを悪用したストリーミング詐欺の拠点のひとつで先日、日本のレコ協も参加するIFPIがブラジルの捜査当局と協力して裁判でクリックファームに勝訴した。先日、記事化した通り欧州大手サブスクDeezerで一日に入稿される楽曲の28%がAI製という事態になっている。ただ防御用のAIで削除を進め、DeezerやSpotify、Apple Musicでは総再生数の1%以下に抑え込んでいる。一方で、記事にある通り楽曲をアップしてもすぐ埋没する課題から、多くのミュージシャンがAIやボットを使ってSNSや動画上で存在感を維持する作業に時間を取られており、記事のアーティストのようにそうしたクリエイティブからかけ離れた習慣に異を唱える話が出てくるのは当然だ。聴き放題で新譜より旧譜が聴かれる時代になり、さらにディストリビューターの普及でDIY音楽が席巻したなか、音楽配信のアルゴリズム(これもAIだ)に自分の新曲を選んでもらうのはレッドオーシャンになっている。歴史的に、こうした反作用が溜まってくると次のイノベーションが起こる経験則がある」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
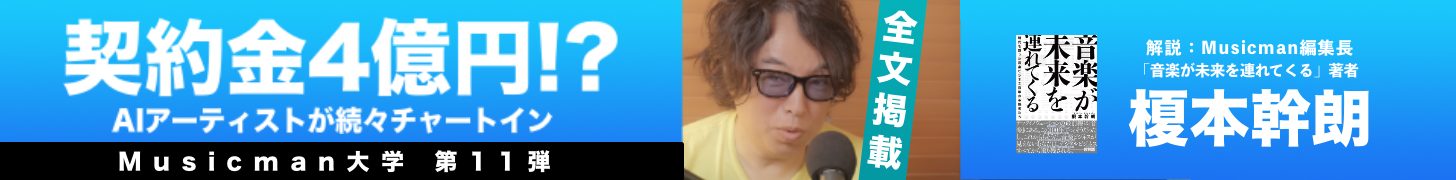
広告・取材掲載