スーパーファン向け製品の展開は、ストリーミングサービスには向かない? MIDiA分析

音楽業界がスーパーファンの収益化に注目する中、英国の音楽専門コンサルティング・ファームであるMIDiAは、デジタルのファンダム向け製品を展開する場所は「今は存在しないのが厳しい現実で、ストリーミング・プラットフォームも適切ではない」との見方を提示。アーティストもレーベルも「小売りの後継者」を必要としていると主張した。
MIDiAは、必ずしも小売りでなくても良いが(例:Bandcamp)、人々が好きな頻度でファンの状態になれて(大半の人は常時ファンではない)、同士と会話し、自分自身を表現し、お気に入りのアーティストのアイテム(物理またはデジタル)にお金を使える場所であることが必要だと分析している。
ストリーミングにスーパーファン製品を組み込むことのリスクは、多様性のある消費者層に対して「音楽と同じようにファンダムを商品化し、一般化してしまうこと」だと指摘。スーパーファン向けサブスクリプションの契約者が増えるほど、「独占的」で希少性が失われると述べた。
ソーシャルプラットフォームの場合は、少なくとも音楽に関しては金銭的消費の効率が悪いと説明している。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「サブスクが普及した後、次の目標とされるスーパーファンだが、どこで展開すべきか?Spotifyのような音楽サブスク上?TikTokのようなSNS上?あるいはWeverseのように独自アプリで展開?音楽業界専門のコンサル会社で有名なMIDiA社がそれぞれの長短を解説。Spotifyでは大きなオーディエンスがいるが、ファンベースになっていないし、アルゴリズムが次々と新しい曲を紹介する環境では音楽ファンが一人のアーティストに固定しない。SNSはファンベースを作りやすいが投げ銭もそこまでではなく課金のカルチャーが弱い。Weverseのような独立系アプリはサービスとして完成しているが、ユーザーのスマホは既にアプリで溢れていて、ゲームやコミュニケーション・アプリなど異業種アプリとレッドオーシャンを勝ち抜かなければならない。MIDiA社は「次の何か」が必要ではと訴えているが、その問いにはまだ誰も明答できないかもしれない」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
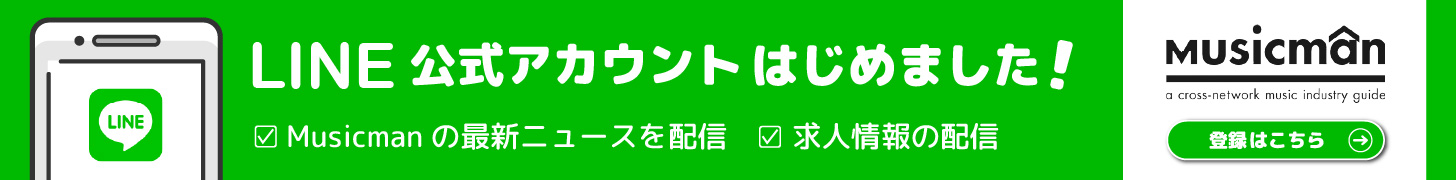
広告・取材掲載