「音楽ストリーミングの未来:変革するか、変革されるか」 MIDiAがイノベーションフレームワーク提示
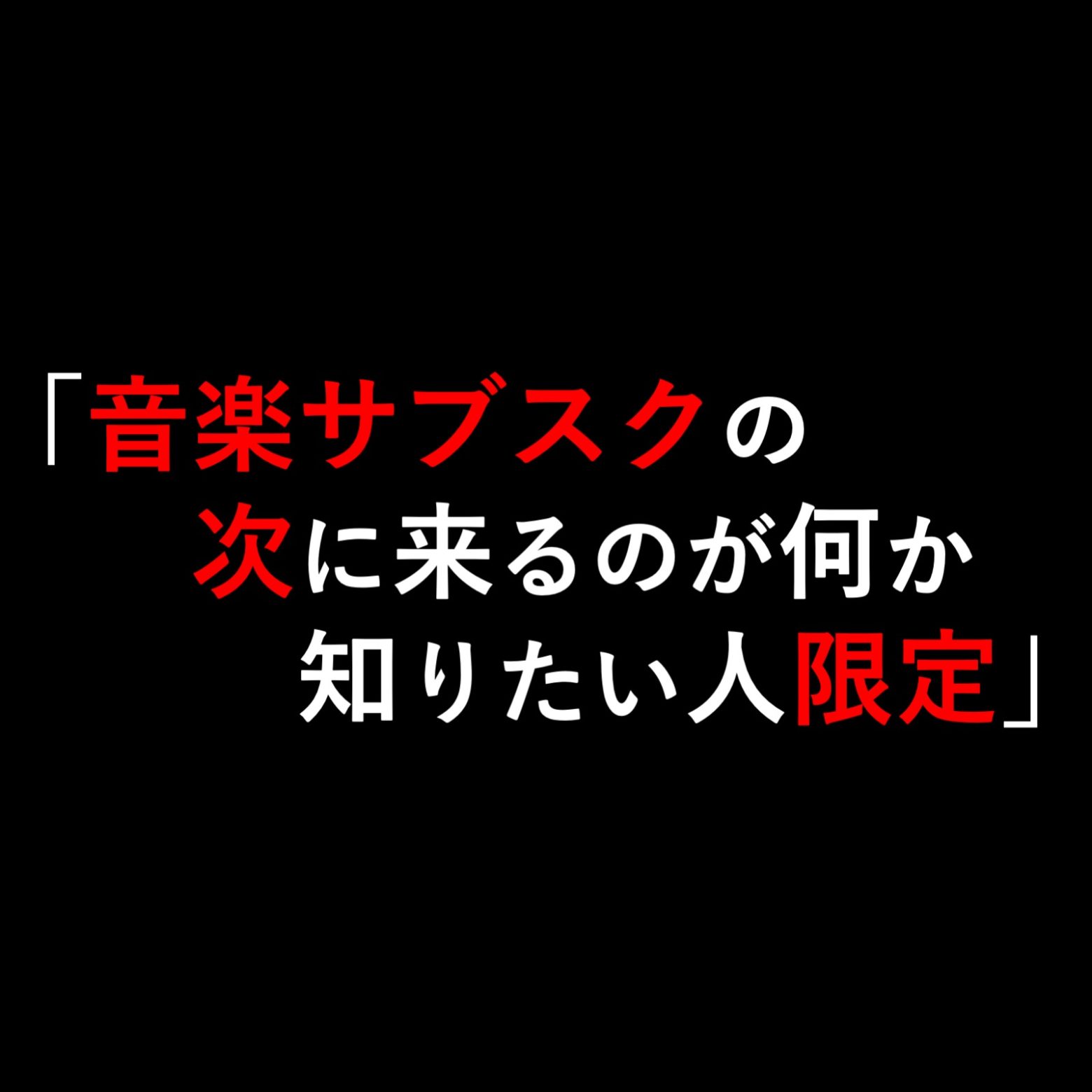
英国の音楽専門コンサルティング・ファームのMIDiAは、ストリーミングが成熟・安定化したことで権利保有者とストリーミングサービスが「最適化」にシフトする中、若年層の音楽消費の変化や値上げによるユーザー離れ、ソーシャル動画とのユーザー時間の奪い合い、生成AIの台頭などの脅威が存在するため、次世代の成長のためには「ユーザーに新しい価値を提供する必要がある」と指摘。ストリーミングの未来を導く重要なイノベーションフレームワーク「BEATS」を提示した。
B – Build Belonging(帰属意識の構築)
ハイパーパーソナライゼーションは価値があるが、「For You」コンテンツは、一体感を呼び起こす機能によって補完されるべき。ライブや「その場にいなければ味わえないコンテンツ」への再投資も含まれる。
E – Elevate Music(音楽の価値向上)
サブスクリプションに価値を見いだす新世代のファンを育てるためには、ユーザー体験の適切なタイミングで音楽を背景から前面に引き出す必要がある。
A – Add Friction(摩擦の追加)
音楽ストリーミングはシームレスになったが、適度な摩擦が好奇心を刺激し、満足度を高め、リスニングを記憶に残るものにする。ただし、それに見合う報酬が伴うことが前提。
T – Tell A Story(ストーリーを語る)
ストリーミングサービスは、音楽に命を吹き込む欠けた文脈を解き明かすことで、単なる消費を超え、アテンションエコノミーで競争できる。
S – Set Rate Limits(制限を設定) ※最重要項目
新しい曲やアーティストで溢れる中、コンテンツの流れをキュレートし管理するメカニズムを再構築する時が来ている。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「重要な話。音楽サブスクもかつてのCDのように成熟期を迎えつつあるが、次はどうなるのか。欧州の音楽産業に影響力の高いマーク・マリガン氏がポスト・サブスクのフレームワークを提案した。ちょっと抽象的に見えるかもしれないが、具体的なイメージは同業者の私が5年前に提示したものと驚くほど似通っている。(B)帰属意識の構築は聴き放題からスーパーファンへの導線を確立すること。(E)音楽の価値向上は、ライブや推し活を好む上の世代と比べ、TikTokやYouTubeのアルゴリズムに慣れた新世代は音楽に受動的なので、彼らをいかに能動的に音楽とか変わってもらうかが次の時代の課題となる。その解決策が(A)摩擦の追加だ。わかりにくいが、要は中国型の音楽サブスクをモデルにしている。中国はSpotify型の音楽サブスクが全く流行らず、苦心の策としてゲーミフィケーションやカラオケなど「音楽を使って遊ぶ」「ファン同士で競う」かたちにしてようやく聴き放題が受け入れられたという先行事例になっている。ここも5年前に拙著で紹介したとおりだ。(T)ストーリーを語る、はMVや短尺動画の羅列で、楽曲が消費されアーティストのファンにまで至らない現状への回答になる。まさにYouTubeがアメリカで実験的に導入したMVを解説するAI DJがその課題意識を如実に示している。(S)制限を設定は、一日30万曲が音楽配信にアップロードされる氾濫状態への危機意識を反映している。それは音楽の民主化といえば聞こえがいいが、生成AIの登場で無数の楽曲が音楽配信に上がることで、需要供給の法則に基づき一曲あたりの価値が必然的に下がってしまうのと、聴かれるべき「本物の音楽」が埋没する可能性が限りなく高まっていくことに対して、レコメンデーションエンジンなどAIで対応するのは限界が既に見えており、音楽業界が協力して「人間」が解決していかなければならない、という主張だ。ここは別のソリューションを私は本で提案していたので(詳細は本に譲る)、こうした業界横断的なアプローチも必要かもしれないなあと勉強になった次第だ」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
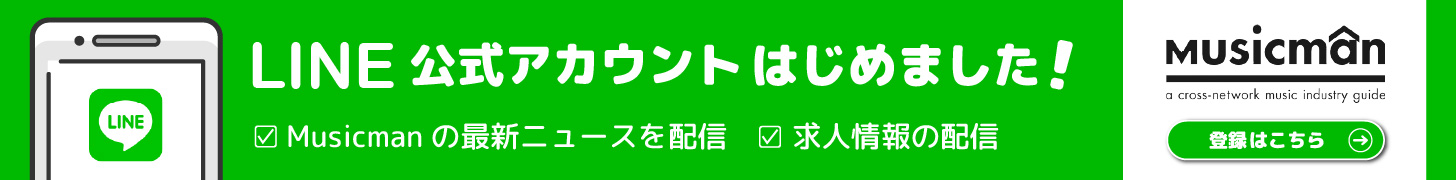
広告・取材掲載