第222回 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 取締役副社長 「TOKYO CALLING」隊長 菅原隆文氏【後半】

今回の「Musicman’s RELAY」は、コロムビア・クリエイティブ株式会社 佐々木健さんのご紹介で、株式会社エル・ディー・アンド・ケイ(LD&K)取締役副社長の菅原隆文さんが登場。
日本最大級のライブサーキット「TOKYO CALLING」の仕掛け人としても知られる菅原さんは、音楽業界のデジタル化を早期から推進し、現在は日本音楽の海外展開にも情熱を注いでいる。LD&Kでの30年近いキャリアの中で培った経験と、音楽への純粋な愛情を語ってもらった。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也、Musicman編集長 榎本幹朗)
▼前半はこちらから!
第222回 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 取締役副社長 「TOKYO CALLING」隊長 菅原隆文氏【前半】
デジタル配信の先駆的取り組み
──LD&Kは早い時期からデジタル配信にも取り組まれていますよね。
菅原:テイチクに入った時に「ノン・パッケージ」という言葉がすでに言われていて、僕も直感的にそうなっていくなと思っていました。2000年くらいからデジタルで音楽配信なども始まっていたので、メジャーがやらない音楽配信を全部やっていたし、Appleの音楽配信もレーベルとしてLD&Kが日本で最初に契約してるはずです。
MPA(日本音楽出版社協会)のデジタル情報研究会(現ビジネスモデル研究会)も20年以上参加しているので、そこにいろいろな会社やサービスの人を呼んで話を聞いてApple、Spotifyといった新しいサービスが始まる前に全部話を聞きに行って、仲良くなったら契約するような形で。
──契約までの障壁もなく?
菅原:向こうからしたらカタログがあるから喜ばれるんですよ。iTunesも最初にやっているし、Spotifyも元Spotify Japanの野本(晶)さんから話を聞きつけて、日本で始まる4年ぐらい前から話してました。
──日本では二の足を踏むような状況だったと思いますが、その根拠はどこにあったんですか?
菅原:ユーザーからしてみたら、自分が聴きたいものがその場ですぐ聴けるというのはものすごいメリットですよね。ユーザーファーストで考えれば、デジタル配信が主流になっていく確信がありました。
──その流れでオーチャードとの関係構築も?
菅原:AppleもSpotifyも全部登録しているから、全部のメタデータを入れなきゃいけないのをうちの規模感でやるのは現実的じゃないなと思って、どこかに一本化して、フィジカルとデジタルのディストリビューションをどちらもちゃんと受けたいと思ったんです。
受託レーベルが100レーベルくらいあるんですけど、それぞれのアカウントをうちのメインアカウントの下にサブアカウントをつけて、各社が自分のパスワードで全部見られるシステムを作れるのはオーチャードだけだったんです。
ユーザビリティを考えた時に、アーティスト単体で自分の事務所みたいな人もいるじゃないですか。そういう人に対して、いつどこで何が回っているみたいなデータを提供できないのは良くないなと思って、それをオーチャードにやってもらったんです。
「TOKYO CALLING」誕生 オンラインのオフライン化の受け皿として
──「TOKYO CALLING」の立ち上げについてお聞かせください。
菅原:僕はいろんなことを5年ごとぐらいにいろんなフェーズで、いろんな音楽業界の方面でやっていて、例えばMPAもそうだし、レコード協会の仕事もやっているし、あと2020年からACPC(コンサートプロモーターズ協会)にも加盟しています。
最初の5年間はテイチクで経理を学んで、その次の5年間はレコード会社と対応するマネジメントの仕事をしました。その次の5年間はレコード会社をやろうと思った時期があって、そのタイミングでタイアップを取るために、テレビ局系の出版社の人を関わることが増えたんですが、テレビとアニメのタイアップがだんだん取れなくなってくるんですね。
それで本当は何をやりたかったかなと立ち返った時に「パンクじゃん!」と思って。パンク・ロックをやりたかったのに、なんで背伸びしてレコード会社を作っているんだ・・・と、ライブ発信に立ち戻ろうと思ったのが2014年なんです。
──そこが転換点に?
菅原:それで2014年にオーディションをやったんですよ。それが「宇田川コーリング」というオーディション企画で、5ヶ月連続で開催しました。2位までを集めて年末にコンピレーションアルバムを出して、コンピをタワーレコードでCDに出して。それで2014年12月にLD&Kのチェルシーホテルとスターラウンジでやったんですけど、チケットが400枚しか売れなかったんですよ。
これからのレコードビジネスをやるにあたって、400枚しか集客がないイベントしか持っていないレーベルにアーティストは集まらないなと。それでちゃんと集客できるイベントを作れるレーベルにならなきゃいけないなと思ったのが2014年で。
──サーキットイベントの難しさを痛感したわけですね。
菅原:ドラマチックアラスカを2013年からリリースしたのですが関西のバンドなんで、関西でいろいろやっているとすごくシステム化されているなと。マーケットが東京よりも小さいから、ジャンルが多少違っても一緒にイベントをやったりとかするんです。
──ここ最近のリレーインタビューでも関西方面の方々が登場なさって、みなさん関係性が濃く繋がっていますよね。
菅原:そうなんです。東京だとイベンター単体で開催しているフェスって少なくて、媒体がやっているフェスをイベンターが一緒にやっている形が多いんですが、大阪はイベンター主催のフェスがたくさんあるんです。
グリーンズもやっているし、清水音泉もやっているし、キョードー大阪、サンクリもやっているし、それぞれの規模の小さいイベントから大きいイベントがあって、ここに出たらこっちに出ます、みたいな。だから、大阪で1年活動するとバンドが大きく成長しているんです。
──東京でもそのシステムを作ろうと?
菅原:それを僕が東京でやろうかなという感じで始めたのが「TOKYO CALLING」なんですけど、2015年になんで東京にサーキットフェスが根付かないのか気づいたんです。
──どんな気づきだったんですか?
菅原:「MINAMI WHEEL」ってとにかく最高じゃないですか(笑)?初めて行った時の衝撃は忘れられなくて。ライブハウスの数もそうだし、立地の関係とか、キャパの設定とか完璧で。
みんなも東京でサーキットフェスをやっているんですけど、町の規模で言うとミナミはでかいんです。それを渋谷と新宿と下北をくっつけたら3日間の連休で30会場、300組のサーキットフェスとして「MINAMI WHEEL」くらいの規模になると思って、思いついたのが2015年12月頃です。
──では、2016年から「TOKYO CALLING」がスタート?
菅原:2016年9月からです。
──今年で10回目の開催になるわけですね。
菅原:今年で10回目ですね。当初からLD&Kのものというよりロックバンドやレーベル、ライブハウスのプラットフォームとして考えていました。10年続けてサーキットとしても大きくなっていったので、今ではシェアリングプラットフォームとして、みなさん使ってくださいという感じです。
──サーキットフェスとしても成熟してきたと思いますが、「TOKYO CALLING」はどのようなコンセプトで開催しているんですか?
菅原:音楽業界とは百年以上続いていて、著作権の制度にしろマネジメントのシステムにしろオンラインがまだない時代に成立しています。音楽ビジネスの仕組みが全部オフラインに合わせてできているじゃないですか。多分それって音楽だけじゃなくて、社会全体に当てはまることだと思うんです。『音楽が未来を連れてくる』ということだと思うんですけど、やっぱりデータとして一番小さいのが音楽だから、最初にデジタル化しやすい。
1995年頃からインターネット革命で、2020年ぐらいにオンラインの世界が成熟してきたと思うんですけど、これからはオフラインの世界がオンライン化していくと思います。その受け皿として何かしなきゃいけない、だから僕はそのタイミングで2016年にオフラインのオンライン化の受け皿として「TOKYO CALLING」を考えたんです。
──10年の成果をどう感じていますか?
菅原:例えばツタロックフェスというイベントがあるんですけど、ツタロックフェスが素晴らしいシーンになったなと思ったのは、お客さんが若い人しかいないんですよ。出演するバンドが若くて、それこそ「TOKYO CALLING」に出てきてくれたようなバンドもたくさん出ています。今のロックシーンって細分化が進んでいるので、ツタロックフェスのお客さんの層がしっかり確立している。その結果フェスとしてとても成功していると思います。
「TOKYO CALLING」がなかったら、最初にバンドを始めるきっかけになるようなイベントが東京ではないと思うし、全員が全員そうじゃなくていいと思うんですけど、やっぱりそこで初めてライブを見た子たちが、大きな衝撃のようなものを10代で経験できる場所が育ってきている実感はすごくありました。
「NIPPON CALLING」コロナ禍での挑戦
──コロナ禍においての状況はどうでしたか?
菅原:コロナの時に音楽業界はすごく元気がなくて、いろんなライブハウスが潰れて、どうなっちゃうのかなと本当に思いました。そこで止まるのが嫌だったので「NIPPON CALLING」というのをやったんです。
全国51のライブハウスに生配信と収録を使って、それを9月に2日間に渡ってやるイベントで。コロナの時に島根とか徳島に行ったりして、「東京から人が来るの半年ぶりですよ」みたいなこと言われながら直接やり取りしながら収録したりということをしました。
──地方の状況はいかがでしたか?
菅原:やっぱり地方が本当に苦しんでいることがわかりました。徳島グラインドハウスとかは、もう本当にもうやっていけない。だからそういう意味で言うと、あのタイミングで実施したことで、僕らもすごく勇気づけられたし、やって良かった試みだったんですけど、めちゃくちゃ大変だったのでもう一回はなかなかできないですね。
──思いついてもそうそう出来ることじゃないですよ。
菅原:使命感みたいなものはあったと思います。あのタイミングで「STAY FREEEE !!!!!!!!」というレーベルを立ち上げたのも今だったらありえなかったと思うんですよね。
──「STAY FREEEE !!!!!!!!」はどんなレーベルなんですか?
菅原:「STAY FREEEE !!!!!!!!」っていうのは、本当にそのまま自由でいてっていうことです。僕は本当に人の言うことを聞くのが嫌で、ずっと子供の頃から、部活もダメだし、先輩の言うことが聞けないんで(笑)、それをそのまま形にしたレーベルです。アーティストにも自由にやってもらいたいし、僕自身も自由でいたいという想いを込めています。
今のところ3バンド(ドラマチックアラスカ、プッシュプルポット、bokula.)しかないんですけど、ツタロックで何組か出させていただいて、2021年から4年半ぐらい続けられているのですごく嬉しいですね。
SXSW参加と日本音楽の海外展開

──今年の3月にはSXSW 2025のショーケースとして、「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO」を開催しています。
菅原:今後の「TOKYO CALLING」の発展型としては、海外に向けてというのは一つキーワードがあるのかなと思います。「TOKYO CALLING」自体は開催し続けていこうと思っている中でプラス、これだけ世の中が変わっていく中で、円安もそうですし、日本の国力が低下することをまざまざと見せつけられる中で、どこかで国のためって言ったら大げさですけど、海外に日本の音楽を届けることも続けていく必要がありますよね。
──現地での反応はいかがでしたか?
菅原:アジア系の人間が中心かもしれないですけども、アメリカでもちゃんと受け入れられ始めています。日本独自の文化としてアイドルもそうだし、アニメやゲームも受け入れられていますよね。じゃあ音楽単体では勝てないのかってなった時、僕は全然勝てると思っています。
SXSWは今年で3回目だったんですけど、日本のアーティストってすごく面白くてユニークな人たちがたくさんいるのですが、メインストリームで勝てるかって言ったら、なかなか難しいかもしれないですけれども、日本の1億人に比べてアメリカは3億人ですし、世界には80億人の人口がいます。そこを広げない手はない。日本は歴史的に見ても文化的な国なわけじゃないですか。それがようやく独自の音楽文化として海外にも広がり始めているタイミングなのかなと思います。
──2023年からSXSWに参加されているんですよね?
菅原:もともと2020年に打首獄門同好会で参加しようとしたんです。でも1週間前にパンデミックでキャンセルになり、それで数百万円が吹っ飛んだので、もうしばらくいいかなと思っていたんですけど、2022年にたまたまニューヨークのライブに行ったときに、PRののスタッフに出会ってSXSWの人間をつないでもらって実現したんです。
──今年はどんなアーティストが参加したんですか?
菅原:当初の予定より少なくなったりしましたけど、今年は打首獄門同好会とEnfants、あと東京初期衝動と眉村ちあきが参加してくれました。
──来年の展望は?
菅原:来年はもっとたくさんのアーティストを連れて行きたいです。例えばSXSWに2000組のアーティストが出るとして、今は日本のアーティストが20組くらいの出演があって、これを100組にしたいなと思っています。
──資金面での課題は大きいですね。
菅原:とにかく交通費もかかりますね。1回行くと数百万かかるので、いろんな人からお金を集めてもらいたいなっていうのは思っています。
──政府の支援についてはいかがですか?
菅原:去年までは全部自腹というか、うちで持ち出してお金を負担していました。今年はCEIPAさんの支援をいただいて開催しました。もちろん潤沢に使える金額ではないので、赤字負担はあるんですけど、日本の音楽を広めたいというお互いの想いから繋がった話だと思うんです。
今回いろんな人に見ていただいたので、それこそ文化庁の方とかJETROの方とかも見ているので、英国、ブリティッシュミュージック・エンバシー(BME)とか、あと台湾のオフィシャルショーケースとか、オーストラリアとかドイツとか、いろんな国が政府の支援を受けたりしてやっているので、日本としてもそういう支援を受けてやっていくべきなんじゃないかなという気持ちはあります。
──日本のマーケットについてはどうですか?
菅原:日本のマーケットって世界で見ると大きいから、国内だけでそもそも儲かっちゃって、ビッグアーティストは別に困ってないんですよね。要するにビッグアーティストが海外に行くことって儲けでみるとマイナスなわけじゃないですか。だけど、それとは別軸で考えた時に直近何年かで見たらそうだけど、やっぱり長い目で見た時に国内だけで戦っていたら絶対に厳しくなっていくと思うんですよね。
──最後に音楽業界を目指す若者たちへのメッセージをお願いします。
菅原:僕自身も音楽業界によくこんなに長くいられるなと思うんですよ。周りもすごくいい人ばかりなんですけれども、めちゃくちゃ売れているアーティストがいるわけでもないですし、それでもLD&Kがここまでちゃんと続けられているというのは、本当にアーティストもそうですけど、関わっているスタッフの仲間がいてこそだと思うんです。これからも大事にしてやっていきたいなと思っています。やっぱり、好きなことを仕事にできることは、本当に幸せだと思うんですよね。
あと10代、20代の子が音楽をやっていることが、いかに素晴らしいことかというのを知ってほしいですね。その影響を受けて変わる人間がたくさんいると思うので、本当に自信を持ってやってほしいなと思います。
最後に、これは僕のエゴなのかもしれないけど、音楽をやる人間は絶対音楽をやめないでほしいなと。個人的にずっとミュージシャンを続けてほしいなと思います。解散しちゃったりするかもしれないですけど、少なくとも僕が関わっているアーティストは、とにかく音楽をやめない方法で人生を歩んで貰いたいですし、アーティストを支えられるようなことをこれからもやっていけたらと思っています。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
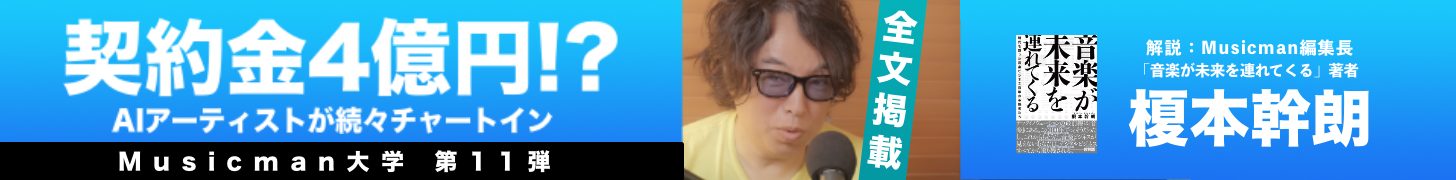
広告・取材掲載