第223回 株式会社ロッキング・オン・ホールディングス/ロッキング・オン・ジャパン代表取締役社長 海津亮氏【前半】
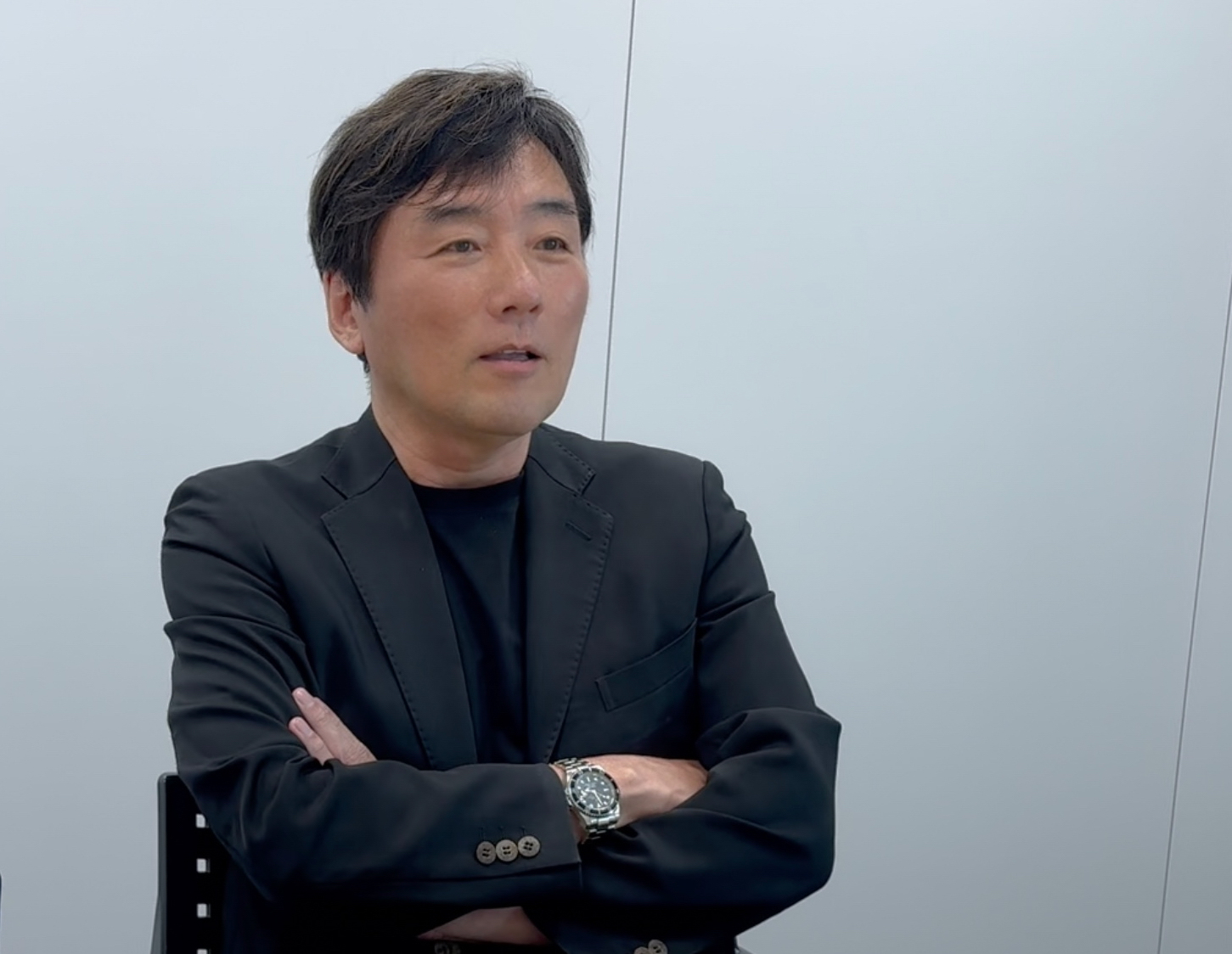
今回の「Musicman’s RELAY」は、株式会社エル・ディー・アンド・ケイ(LD&K)取締役副社長 菅原隆文さんのご紹介で、株式会社ロッキング・オン・ホールディングス/ロッキング・オン・ジャパン代表取締役社長 海津亮さんが登場。
海津さんはキョードー東京を経て、松任谷由実の所属事務所・雲母社(きららしゃ)でコンサート制作等を19年間担当。2007年にイベント部長としてロッキング・オンに入社し、2024年4月から代表取締役社長に就任。
2000年の第1回開催から四半世紀を迎えた日本最大級の野外ロックフェスティバル「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」をはじめ春の「ジャパン・ジャム」、冬の「カウントダウン・ジャパン」など総称「Jフェス」の運営を統括し、音楽業界の未来を切り拓いている海津さんにその歩みとロッキング・オン・グループの未来について詳しく話を伺った。
※本インタビューは6月下旬に行いました。その後、7月14日にロッキング・オン・グループ会長の渋谷陽一さんがご逝去されました。故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也、Musicman編集長 榎本幹朗)
手塚治虫と荒井由実に影響を受けた幼少期
──慣例に従いまして、まずご紹介いただいた菅原さんとのご関係についてお聞かせください。
海津:菅原さんと知り合ったのは12年ぐらい前ですね。きっかけは、今年から復活したんですけど、「RO JACK」というロッキング・オンが主催するアーティストのオーディションをやっていて、その責任者が僕だったんです。
当時、菅原さんが手掛けているアーティストがエントリーして、優勝アーティストが原盤を作ってCDをリリースするという仕組みだったので、権利のことなどを説明する会があったのですが、そこに後見人としていらっしゃったんですよね。それ以降、打首獄門同好会やドラマチックアラスカ、日食なつこなど、うちのフェスにも出演してくれているアーティストとの関わりも増えてきました。
ちょうど彼が「TOKYO CALLING」を立ち上げようと準備していたタイミングで、僕は若手のアーティストとのコンタクトポイントを増やそうと能動的に動いていたタイミングだったので、いろんな地方のサーキットイベントのオーガナイザーを紹介してくださったり、付き合いが深くなっていったという感じです。
──菅原さんは最初から決めていたかのように、迷わず海津さんの名前を挙げていました。では、ここからは海津さんご自身のことをお伺いしたいと思います。まずお生まれは?
海津:東京・大田区の馬込というところです。住宅街の中にあって、大家族で大きい家だったんですよ。祖父が理容業界の結構偉い立場の人で、理容の専門学校の校長をやっていたり、業界団体の理事長みたいなことをやっていて。高度経済成長期でオフィス街がどんどん発展していた時に、丸の内とか赤坂とかのオフィスビルの中に理容室を多角的に経営するという事業をやって、そこのオーナーだったわけですね。それで理容学校の方の生徒が、今でいうインターンみたいな形で各理容室で働いていて、その中の地方出身者を家に住まわせていました。
その人たち用の部屋が2部屋あって、男女がそれぞれ部屋を分けて住んで、自分の家族も7人家族でしたが、家族とは別にそういう人たちが家にいて、家の中に一つの社会があるみたいな。そんな環境で自分の社会性や外交性みたいなものが育まれたのかなという感じはしますね。
──今のフェスにもつながるような話ですね(笑)。
海津:インターンの人たちが喧嘩したり、10代後半から20代前半の若い男女が一つの屋根の下にいるわけだから、恋愛関係にもなったりとか・・・そういうのを子供時代に見ていましたね。
うちの父親はその祖父を継いで理容チェーンを経営していたんですけど、70年代に男も長髪が流行っていくわけですよ。そうすると床屋に行く頻度が変わって、理容業界の経営が一気に厳しくなって…父は「ロックのせいだ」って言っているんですけど(笑)。多角的にやっていたのに、ある時父は決断をして店を全部売っちゃって辞めるんですよ。そこから1年か2年勉強して、税理士になるんですけど。
──床屋から税理士に?
海津:家族が7人いて養わなきゃいけないから、店への愛着はあったと思いますけど・・・そういった賢いリアリズムなんですよね。そこが渋谷(陽一)にすごく似ているんです。そういう親に育てられたから、僕も渋谷と波長があったのかなって思ったりもします。
──家族はどんな構成だったんですか?
海津:祖父、祖母、両親、兄と僕と妹ですね。僕の話で言うと、誕生日が3月27日なんですけど、早生まれで、クラスの中で一番誕生日が遅いんですね。かつ、今でいう早産児で、本当は5月生まれのはずだったのが3月に1800グラムとかで生まれちゃったんですよ。だから幼稚園に行くと、子供の中に赤ちゃんが一人混じっているみたいなものですごく大変だった記憶があります。
──実は僕(屋代)も3月生まれです。
海津:幼稚園のカリキュラムで、「スプーンじゃなくてお箸を使えるようになりましょう」みたいなことも僕だけ最後まで使えなくて、お弁当を最後まで食べられない。しかも僕、左利きで。当時は親が矯正するから、少なくとも鉛筆とお箸だけは一旦右に直させられて、そういう何重ものハンディがあって。
──3月生まれのあるあるですね。3月生まれで、左利きという海津さんとの共通点を見つけました(笑)。
海津:(笑)。幼稚園の頃は周りのみんなから劣っていたという、そういった思い出しかないですね。幼稚園の時はコンプレックスがあったけれど、学区の関係で幼稚園時代の子たちとはあんまり小学校で一緒にならなかったんですよ。
それで小学校の6年間で身体がすごく大きくなって、中学になったら幼稚園時代の子たちとまた同じ中学になったんです。僕は大きくなっているから、これは初期設定をし直そうと思って(笑)。幼稚園の時とは違うからと、関係性をリセットしましたね。
──向こうは驚いていましたか?
海津:「おお、久しぶり!」って肩をギュッと掴んだりとか(笑)、そんな感じでしたね。話を戻すと幼稚園時代は終わって、小学校に入ってから半径5メートルより外のことに興味を持ち出したのが、小学校2年生ぐらいです。
八王子の隣の日野に住んでいる10歳年上と7歳年上のいとこがいるんですけど、2人のことがすごく好きで、夏休みとかになると長期間泊まりに行っていました。その2人がいろんなカルチャーをインプットしてくれる役割だったんですよ。70年代前半ですから最初に教わったのは漫画なんですが、それが自己形成に影響していて、手塚治虫とかを読んですごく興味を持ったわけですよね。
──海津さんは何年生まれなんですか?
海津:1964年生まれです。
──64年、東京オリンピックの年ですね。『鉄腕アトム』はリアルタイムの時代じゃないですね。
海津:『鉄腕アトム』も読みましたが、『火の鳥』『ジャングル大帝』『W3(ワンダースリー)』とか、ちょうどその頃、『ブラックジャック』の連載が始まりました。一番好きだったのが『奇子(あやこ)』という作品で、当時ビッグコミックに連載していて。大戦で捕虜になった主人公が帰国後GHQのスパイになって後の下川事件のテストとなる轢死事故を東北の田舎で起こしたり、小学生じゃ普通は読まないですけど、いとこの家で読んで漫画の面白さにハマっていきました。
──じゃあ、ちょっと大人びた少年だった?
海津:そうだったかもしれません。結構大人っぽい作品が好きでした。音楽もその2人からすごく影響を受けていて、小学5年生の時に荒井由実の「ひこうき雲」をリアルタイムで聴かせて貰ったのが運命だったかと。もともと歌謡曲が好きで紅白の曲をいっぱい歌えるような子供だったんですけど、荒井由実を聴いた時に衝撃を受けてレコードを借りてずっと家で聴いていました。
──「ひこうき雲」はアルバム?
海津:アルバムです。はっぴいえんどや大滝詠一のソロアルバムもあったんですけど、そういうのもたくさん聴かされて。グループサウンズや日本のフォーク、ロックの後には、ローリング・ストーンズとビートルズのシングルなんかを順番に聴かせてもらいました。
──そのいとこが漫画に限らずたくさんレコードも持っていたんですね。センスが素晴らしいというか、名アーティストばかりですね。
海津:その影響もあって64年生まれなんですけど、少なくとも5歳年上ぐらいの人の原体験とカルチャーが、だいたいイコールなんですよね。そうすると小学生だから、夏休みが終わると、そこで仕入れてきたものを「手塚治虫ってすごいぞ」「荒井由実ってすごいぞ」とクラスメイトに布教活動するわけですよ。
──伝道師のようですね。では、そういったカルチャーに目覚めて、スポーツはあまり興味が無い感じでしたか?
海津:そうですね。体格がいいので「運動は何をやっていたんですか?」とよく聞かれるんですけど、いつも「帰宅部です」と答えています。野球と相撲は見るのは大好きなんですけどね。
中学時代も引き続き音楽が好きで、レッド・ツェッペリンが好きになって、中2の時に初めて『rockin’on(ロッキング・オン)』を買いました。ロバート・プラントが表紙の号をジャケ買いというか表紙買いでした。
そこに書かれているそれぞれのライターのキャラクターがすごく好きになって、渋谷陽一という存在に出会うわけです。渋谷の書く文章は音楽評論でもあるんだけど、メディア論であり、コミュニケーション論であり、組織論でもあるみたいな。そういう思想にすごく感化されて、間違いなく自分が一生で一番影響を受けた人間は渋谷陽一と言えますね。
音楽と映画に触れる日々からコンサートスタッフに
──そういった背景をお聞きすると、今この会社にいることは必然のように感じます。高校時代はどうでしたか?
海津:高校生の時には今や伝説的な番組になっていますけど、「サウンドストリート(※NHK-FMで1978年11月23日から1987年3月20日まで放送された音楽番組)」を聴き始めて。当時はネットもSNSも無いですから、サウンドストリートが音楽の情報源でした。
月曜日が松任谷正隆さんで、火曜日が森永博志さんで、水曜日が甲斐よしひろさんで、木曜日・金曜日が渋谷陽一。その後、月曜が佐野元春さんになって、火曜が坂本龍一さんと・・・今言った方々全員、深い付き合いになっているので不思議な縁ですね。
──帰宅部が故にカルチャーに触れる時間もたくさんあったわけですね。
海津:帰宅部だから『rockin’on』を買い続けて、サウンドストリートを毎日聴いて、映画も好きになって観始めるんですよね。高校1年の時にコッポラの『地獄の黙示録』を観た時にも衝撃を受けて。ベトナム戦争の極限状態の狂気、その後の宗教性の狂気みたいな、哲学的なテーマなんだけど映像の説得力がものすごいわけですよ。その流れでコッポラ、ルーカス、スピルバーグ、マイケル・チミノ、ブライアン・デ・パルマとか大好きになって。そういうアメリカニューシネマ系から最初は入るんだけど、そこからゴダール、トリュフォーとかヨーロッパ映画も観るようになりました。
──ロードショーで見たんですか?
海津:『地獄の黙示録』はロードショーで見て、『タクシードライバー』は名画座ですよね。ヌーヴェル・ヴァーグは全部、名画座でした。
──ずいぶんとアカデミックな学生ですね。『ぴあ』が創刊された直後ぐらいの世代ですか。
海津:当時はそういう学生がいっぱいいましたけどね。僕が映画を見るようになった頃は、『ぴあ』と『シティロード』ですね。ロッキング・オンもぴあも1972年の創刊ですから。
──では、引き続きカルチャー三昧ということで。バンドをやろうとかは思わなかったんですか?
海津:思いませんでした。「楽器を持とう」って人とはロックに対するアプローチが違ったんでしょうね。自分がロバート・プラントになれるなら、話は別ですけど(笑)。
──で、高校を無事終えられて次は進学ですか?
海津:東洋大学の経済学部に入るんですけど、あまり真面目な学生じゃなかったです。大学では映画研究会に入るんですけど、映画の歴史を研究するような会で居心地が良かったですね。
──その時は何か文章とか評論って書いていたんですか?
海津:良く書いていました。高校生の時に『rockin’on』にデヴィッド・ボウイのベルリン三部作のその後・・・みたいな投稿をしてボツになったこともありました。
──その話は、渋谷さんにもしたんですか?
海津:本人に話をしたことはありますけど、同じような人はたくさんいましたから。その映画研究会に入りつつ、大学生なので何かアルバイトをしようと思いケン&スタッフという会場整理、警備、イベントサポートの大手の会社にアルバイト登録をしたんです。
──最初はどんな会場だったんですか?
海津:最初の会場が、83年の武道館でデヴィッド・ボウイのシリアス・ムーンライト・ツアーという「レッツ・ダンス」の時のワールドツアーなんですけど、これは良いバイトだなと思って。
──そこは洋楽専門なんですか?
海津:当時はウドー、キョードー東京、SOGOとかのイベンターをクライアントにしているアルバイト会社で。最初はアーティストの公演をタダで見られるかも・・・と、ある種不純な動機で始めましたが、やっていたらどんどん面白くなっていきました。
例えば武道館だったら、アリーナに100人ぐらい係員がいるわけですよ。アルバイトの中にチーフやサブチーフという階級ができていて、その人たちは同年代なんだけど、他のバイトを指揮する。で、僕自身は体育会系に所属したことがないから、秩序があってそれを同世代なのに仕切れるチーフを見て、ああいう風に人間として成長しなきゃいけないなと非常に感化されて。
その中に、すごく尊敬できる1歳年上のチーフがいたんです。その人から学ぶことがいっぱいあって、僕もバイトの中で一応戦力になるということで、どんどん位が上がっていったんですよね。で、その尊敬する先輩が大学4年になって就活する時に、次の代のチーフに僕が任命されました。
──すごいですね。
海津:現場を仕切る経験は今の仕事にもつながりますけど、人をマネジメントするということもそこで学ぶことができました。いざ自分が大学4年になったら、これまたいい加減で就活をほとんどしなかったんですけどね(笑)。
映画の配給会社に就職したいなと思って、東宝東和、フランス映画社とかそういう大きいところをいくつか受けて、12月ぐらいに最終面接までいったので受かると思っていたら落ちちゃったんですよ。
──どうして受かると思っていたんですか?
海津:いや、ただの思い込みですよね。映画の話で盛り上がったとか、面接の時になんか手応えがあったといいますか・・・だから落ちた事がすごくショックで、卒業してからどうしようかなと思っていたら、アルバイトをしていた時のつながりで、キョードー東京から「ウチで働かないか」と誘われて入社しました。
新入社員初仕事はチンパンジー・バブルス君の担当
──流れとしてはキョードー東京の方が自然ですね。
海津:そのまま一直線に進んでいる感じはしますね。
──その頃の社長は山崎(芳人)さん?
海津:内野(二朗)さんが辞めて、嵐田(三郎)さんに入れ替わった時ですね。入った年の6月にマドンナの初来日公演があったんですが、後楽園球場が台風で中止になっちゃって結構な暴動騒ぎになって。入社1年目でショッキングな出来事でした。
それで秋にはマイケル・ジャクソンの初来日公演があって、これもめちゃくちゃな盛り上がりですよね。大きい現場なので社内で体制を組むじゃないですか?君はマイケル・ジャクソンのロードマネージャー、君はバンドメンバー、君はプロダクション、ステージスタッフ・・・と振り分けていたんですが、僕は新入社員だったのでチンパンジーの※バブルスの担当(笑)。
※長年にわたりマイケル・ジャクソンと一緒に生活したチンパンジーで、バブルス君の愛称で知られる。
──(笑)。
海津:その話を「rockin’on.com」で書いているので(マイケルとバブルスの思い出)、今でも初めて会う人にその話を聞かれることが結構あるんですよね。
──バブルス君のお世話係って、餌をあげたりするんですか?
海津:そうです。キョードー東京が表参道なので紀伊國屋でバナナを買って、泊まっているキャピトル東急に行くとバナナに飛びついてきて、だんだん仲良くなりました。最終的にすごく懐いてくれたんですが、日本のCMに出すみたいな話があって連れてきたけど、何らかの理由でそれがダメになって、ツアーの半分ぐらいの段階で帰国することになったんです。
──キョードー東京では洋楽を担当していたんですか?
海津:マドンナとかマイケルみたいな洋楽もやるんですけど、基本的には邦楽のセクションへの配属されてました。それで、松田聖子やユーミンなどの現場を担当するようになったのですが、ユーミンに関しては小学生時代の音楽の原体験なので、関われたことがとにかく嬉しくて。
入社して1年目に「ALARM à la mode」というツアーの武道館公演、2年目は「ダイアモンドダスト」というツアーを武道館公演でやって。3年目が「Delight Slight Light KISS」というアルバムが出たんですが、「荒井由実」の時と「守ってあげたい」の時と、その次ぐらいのユーミンブームがきていました。
雲母社への転職と渋谷陽一との初対面
──日本で最初にスペクタクルショーのコンサートを作り始めたのは、やっぱりユーミンのイメージですよね。
海津:そうですね。龍が出てきたり、象が出てきたり、ということを80年代からやっていましたからね。日本でバリライト(ムービングライト)を初めて使ったのはユーミンじゃないのかな。そのライティングとか、電飾とかが音楽に同期するシステムを、世界で初めて作ったのがユーミンのチームなんですよ。
それで、僕がユーミンを担当した3年目がちょうどLPからCDにフォーマットが変わる時で、そういう時にハードを普及させる起爆剤になるソフトがあるじゃないですか?ユーミンのCDが正にその起爆ソフトとなって200万枚とか売れて、CDプレーヤーを一気に普及させたわけですよね。
その影響でユーミンの事務所の雲母社はてんやわんやの状況になっていて、先程の「Delight Slight Light KISS」ツアー最後の横浜アリーナこけら落とし公演でで大竹さんというユーミンのチーフマネージャーに「うちに来ないか」という打診をされたんです。
──じゃあ、キョードー東京には3年いたんですか?
海津:2年ちょっとですね。
──キョードー東京からの引き止めは無かったんですか?
海津:無くは無かったですけど、キョードー東京も僕の一生を面倒見られる訳でも無いですし。
──では、雲母社のいわゆるライブ責任者みたいな形で入った?
海津:最初はチーフマネージャーのアシスタントからですね。ちょっと話が前後するんですけど、渋谷と僕が初めて会ったのはキョードー東京の時なんですね。招聘するアーティストが決まったら、ロッキング・オンで取り上げてくださいとプロモーションするわけですよ。
それで「『rockin’on』の読者で好きならお前が担当しろよ」と言われて、前任の方と「今後はこいつが担当しますから」と『rockin’on』の編集部に挨拶に行くんです。その時に渋谷がいて、自分の人生においてどれだけ『rockin’on』が重要で、『rockin’on』が好きかみたいなことを渋谷の前で熱弁したんですよ。そしたら、渋谷は「はあ・・・」みたいな薄い反応で「たまにそういう人が来るんだよね。だけど、出世しないんだよ。」と言われて(笑)。
──クールな返答ですね(笑)。
海津:それで笑っちゃったんですけどね。渋谷はユーミンが大好きだから、僕が雲母社に移るという挨拶をしに行ったらすごく喜んでいました。『BRIDGE』という雑誌が創刊した時に、ユーミンが初期に連載を持っていたんですけど、そういうのも渋谷から相談がきましたね。
──雲母社には何年いらっしゃったんですか?
海津:19年です。
──そんなにいたんですか。では、あらゆるユーミンのツアーは海津さんが関わっていた?
海津:そうですね。後半はロシアのサーカスと、シンクロナイズドスイミング等と一緒に組んだ「シャングリラ」というシリーズを、99年と2003年と2007年にやって。99年の時には仮設のプールを作ったり、人工アイススケートリンクを作ったり。3では、シルク・ドゥ・ソレイユの「O(オー)」っていう、ラスベガスのベラージオでやっている常設のショーを参考にして、プールがすのこ状のリフターを使って一瞬で舞台になるという機構を仮設で造ったり、本当に特別な体験ばかりでした。
──いや、本当に羨ましいお仕事ですね。
海津:2000年過ぎぐらいからは、アルバムのプロモーションにも主体的に関われるようになって、その時に作った媒体との人脈みたいなものは今にも活きているんですよね。
──それはテレビやラジオ?
海津:そうです。テレビやラジオ、地方のFM局や、渋谷との関係は元々深かったけど、音楽評論家の先生方とか。大きなアーティストとの仕事をしてないと得られない、特別な人脈に出会えることは本当にありがたかったと思いますね。
──超大物アーティストのマネジメントに関わる人たちの特権ですよね。
海津:そうかもしれないですね。あと雲母社の話で面白かったのは、松任谷(正隆)さんがステージに対してもですが、新しいテクノロジーとかシステムみたいなものに対してものすごくアンテナを張っていて、インターネットに対する興味も早かったんですよね。
95年頃から、インターネットでのプロモーションをやり始めて。当時はまだWindows95が出る前だから、一般の人はほとんどパソコンも持ってない時代ですよ。でも松任谷さんのチームでは、早い段階からウェブサイトを作って、ファンとのコミュニケーションを取ろうとしていました。今だったら当たり前なんですが、マネージャーやスタッフがSNSでいろいろ発信するのがプロモーションの基本になっているけど、そういうことも先駆けてやっていて。
そうしたら、なぜか海津亮のページを作った物好きなユーミンのファンの方がいて、最初は不気味なので放置してたんだけど、徐々にいろんな情報を僕がそこに発信し出したら一番コアなファンが集まってきて、口コミやネットでどんどん拡散していくみたいな、そういうプロモーションのフォーマットが自然に出来上がっていたんです。
──すごい先見の明ですね。
海津:僕もその頃からインターネットの可能性というか、メディアの未来みたいなものを考えるようになって。結果的に、それが後のロッキング・オンでの仕事にもつながっていくんですけどね。
▼後半はこちらから!
第223回 株式会社ロッキング・オン・ホールディングス/ロッキング・オン・ジャパン代表取締役社長 海津亮氏【後半】
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載