ストリーミング嫌いのZ世代、YouTubeやTikTokで音楽を発見
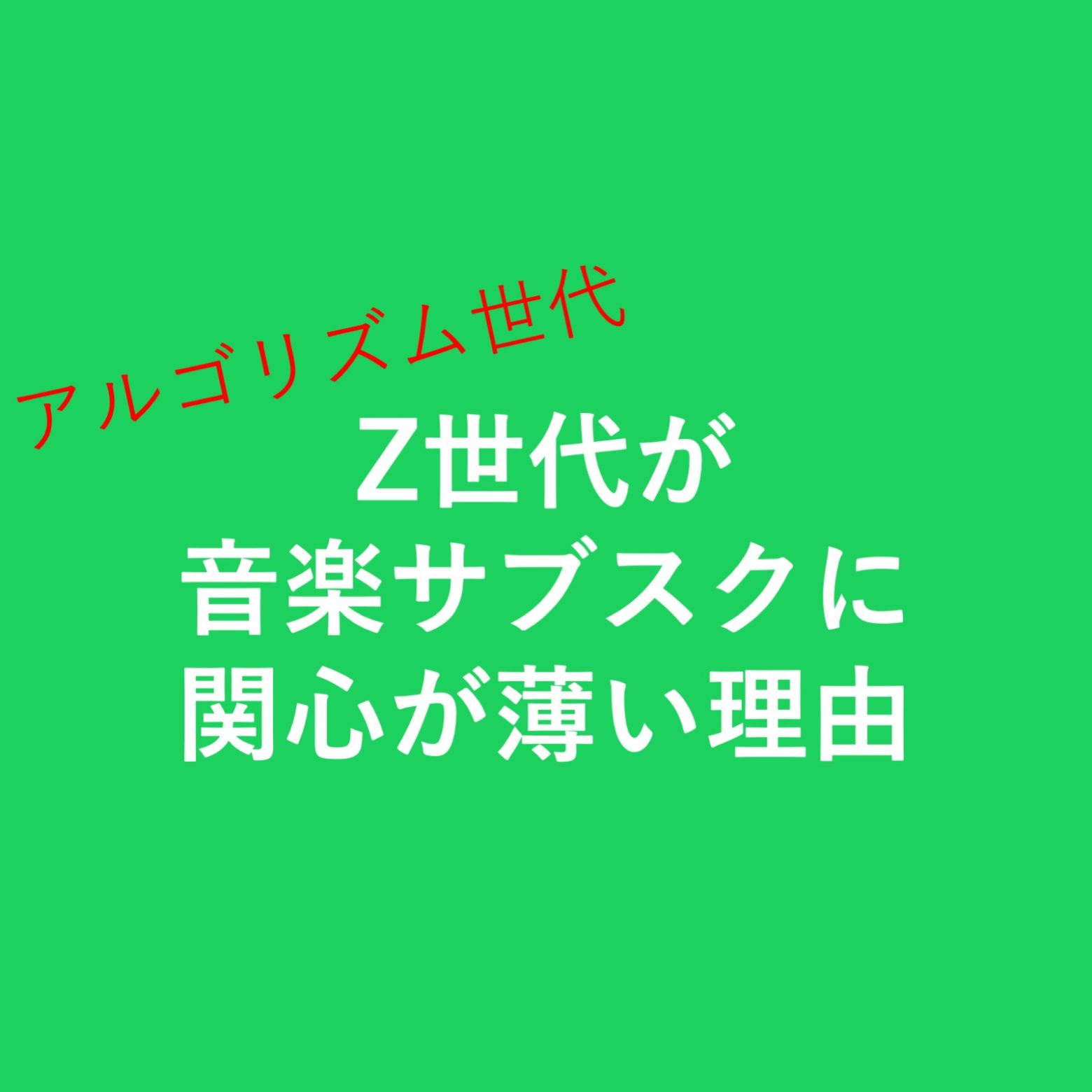
音楽に対して最も感受性が強いと言われる12〜24歳に当たるZ世代の音楽消費の傾向について、音楽プロデューサー/エンジニアのボビー・オウシンスキー氏が分析している。
英国の音楽専門コンサルティング・ファームのMIDiAは、Z世代はストリーミングになじんでいない兆候があり、16〜19歳におけるストリーミングの普及は他の年齢層よりはるかに遅いと指摘。米調査会社NuVoodooによると、音楽のほとんどをYouTubeやTikTokで、しかも短編動画から得ている。短編動画は、注意力の持続時間の短さに加え、BGMで受動的に聴く傾向があることも好まれる要因という。
オウシンスキー氏は、能動的に新しい音楽を探す必要がないため、Z世代は音楽とのつながりを築くのが難しくなっていると指摘。一方で、音楽ビジネスに影響を与えるであろう性質として、古いヒット曲が好きで、ソーシャルメディアで名作を見つけるのを楽しみ、物理的なメディアで音楽を所有したいという願望があると説明した。
カタログ、ライセンス、フィジカル製品ブームなどで利益を得るのは実績のあるアーティストであることから、今後はさらに新人のブレイクが難しくなるとみている。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「重要な記事。Z世代が音楽サブスクを使いこなしているかといえばそうではないという分析。理由はTikTokやYouTubeで音楽を聴くのを好み、アルゴリズム主導の受動的なリスニングに慣れた結果、音楽を積極的に聴こうという気持ちが薄いとMIDiA社は分析する。Z世代より上の世代のように、体験を求めライブへ行くというふうには簡単にはいかないということだ。同社はイギリスに拠点を置く音楽産業専門のコンサルティングファーム。ある意味、私と同業者だ。動画、SNS、アニメ、漫画、ゲームと音楽に限らず娯楽が拡散しており、目下、音楽産業は他の娯楽や様々なプラットフォームと結びつきを強めることでリスナーの確保を図っているが、受動的な世代を能動的な音楽ファンに変えていく点では私を含めまだはっきりとした回答を得ているわけではない。個人的にはかつてのパーティー→カラオケのように、何か音楽を使った新しい遊びが求められているのだろうという気がする。また名曲を好み、所有欲を満たしたい願望が強いのは古い世代だけでなくZ世代も同じという状況は、スマホや音楽サブスクの次に来るべきイノヴェーションの土壌になるだろう。」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載