ワーナーのロバート・キンセルCEO、音楽業界と自社の将来像を語る

ワーナー・ミュージック・グループ(WMG)のロバート・キンセルCEOが10月8日、ブルームバーグ主催カンファレンスに登壇。Music Business Worldwide(MBW)がポイントをまとめた。
同氏は、所属アーティストや楽曲を題材にした映像作品の制作を巡るNetflixとの提携報道は肯定しなかったが、動画配信分野における発表が間近であることを示唆。自社を「音楽界のマーベル」と称し、保有カタログを未開拓のコンテンツ資源として位置付けた。
AIの台頭については、音楽がさらに増え、認識不能な音楽も急増するが「有名アーティストによるAI音楽、認識可能な音楽、一種のブランド化された知的財産やスターの音楽こそが、より価値を持つと確信している」と述べた。
音楽業界で起きている最も重要な変化の1つとしてストリーミングサービスの価格設定を挙げ、契約者数の増加に依存した成長から転換点を迎えていると指摘。自社は過去12カ月で市場シェアを1ポイント伸ばし「ワーナー・レコードとアトランティック・レコードの両エンジンが全開で稼働している」と説明した。
今後は特に米国と英国市場において「業界全体としてフルサービス企業へと進化する」との見方を提示。これら市場では従来レーベルがマネジメントやライブプロモーションサービスを提供してこなかったが、複雑化する業界においてアーティストにはより大規模で統合された企業の支援が必要だと主張した。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「世界三大レーベルの一角ワーナーミュージックのキンセルCEOが講演。カタログ資産の活用、AI時代におけるスターの価値、ライブビジネスの強化、音楽サブスクの価格改定について語った。カタログ資産については、聴き放題の時代に入り日米ともに旧譜の再生割合は7割ほどになっている。TikTokやNetflixなどを通じて旧譜がバズる事例も増えてきた。AI時代におけるスターの価値については最近、Sunoで音楽を作るAIアーティストのザニア・モネにメジャー契約をオファーしたことがモネの制作者テリシャ・ジョーンズの著作で明らかになっている。なおモネにはユニバーサルミュージックもオファーを出しており、契約を勝ち取ったのはディズニー系のハリウッド・レコード。この件は、無名のAIアーティストではなくファンを巻き込んで盛り上がったIPとしてのザニア・モネに大手レーベルが着目したので、キンセルCEOの講演と矛盾は無い。ライブビジネスの強化というのは、日本で360度ビジネスと呼ばれるもので、レーベルが音楽事務所のようなアーティストマネジメントをやる他、ライブのプロモーションも手掛ける形。ワーナーはアメリカ、イギリスでその面が弱かったので強化するようだ。音楽サブスクの価格改定については、主にアメリカ・イギリスでサブスクの普及が終わり、会員数を増やすよりも単価を上げる、つまり値上げを進める方針。以上から目新しい方針変更は講演で語られなかったが近年、それぞれの戦略の具体化が進んでおり、それがシェア拡大につながっている自信を感じさせる講演内容だった」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
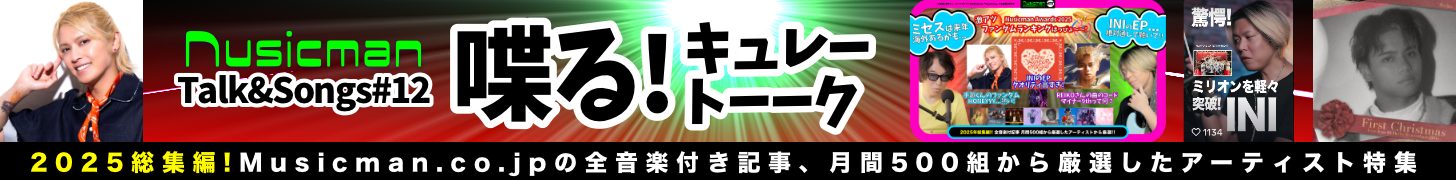
広告・取材掲載