音楽業界、AI音楽の検出技術を構築中 「削除でなく、ライセンスとコントロールが目標」
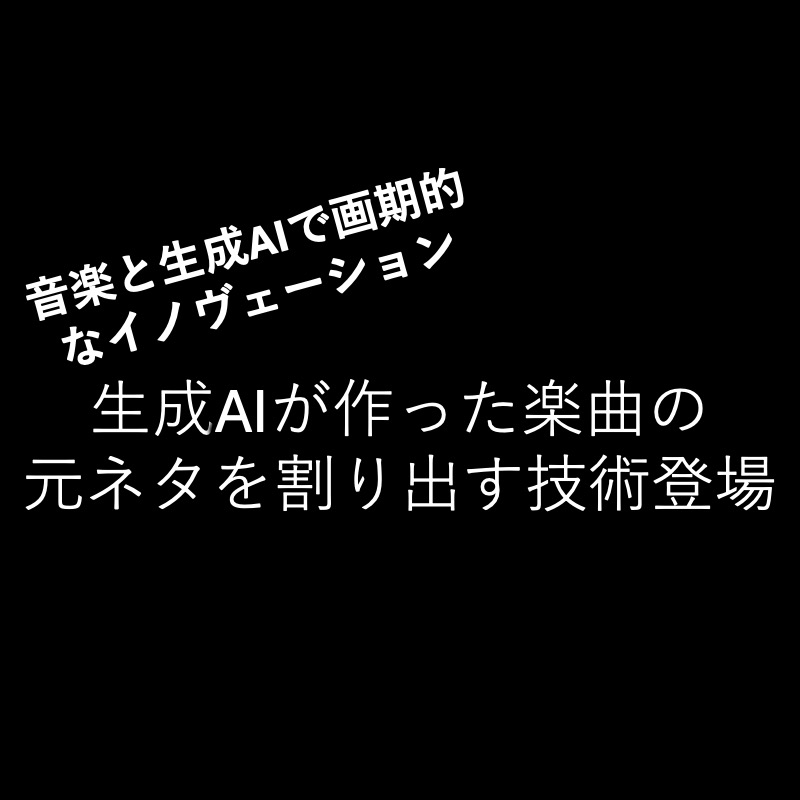
AI音楽の台頭が懸念される中、削除するためでなく、追跡可能にするために構築された新たなインフラが静かに構築されつつある。検出システムが音楽パイプライン全体に組み込まれ、AI音楽を早期に特定し、メタデータでタグ付けして、どのように移動するかを管理することが目指されている。IT系メディア「The Verge」が伝えた。
現在、ライセンシングのワークフローに検出機能を組み込むスタートアップ企業が続々と登場している。YouTubeやDeezerのようなプラットフォームは、アップロードされた合成音声にフラグを付け、検索やレコメンデーションでどのように表示されるかを設定する内部システムを開発。Audible Magic、Pex、Rightsify、SoundCloudなどは、トレーニングデータセットから配信に至るまで、検出、モデレーション、アトリビューション機能を拡張している。
VermillioとMusical AIは、完成したトラックをスキャンして合成要素を検出し、メタデータに自動的にタグ付けするシステムを開発。VermillioのTraceIDはステムレベルで模倣を検出できる。
VermillioはAI音楽の削除ではなく、積極的なライセンシングと認証されたリリースに焦点を当てており、TraceIDのようなツールによる認証ライセンシングは2023年の7,500万ドルから2025年には100億ドルに成長すると予測している。
Spawning AIのDNTP(Do Not Train Protocol)は、データセットレベルで検出。このオプトアウト・プロトコルにより、アーティストや権利所有者は作品をモデル訓練の対象外とするラベル表示ができる。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「何気に重要なニュース。音楽に限らず一度、生成AIでアウトプットされたら元の学習素材がわからないというのが大問題だったが技術革新が進み、音楽に関しては例えばSunoで生成した曲の元ネタとなった楽曲をある程度、特定できるようになりそうだ。既にAIで生成した楽曲を検出→削除するAIは実用化され、Spotifyなど大手サブスクが導入しているようだが、今回のは音楽業界が生成AIを積極活用する未来を切り開く可能性を持つ。世界の音楽業界は既にSunoやUdioを裁判で訴えつつ、同時にライセンス交渉も進めているが、鍵となるのがAI企業側の自己申告がなくてもどの楽曲が元ネタになっているか割り出して自動的にライセンスできるようにするテクノロジーだった。欧米の裁判所に関係なく著作権のある楽曲をAIの学習材料に出来る国がこの分野で急進しており、生成しても元の素材が割り出せるなら対応の仕方も出てくる。中国のDeepSeekショック以来、英政府や米トランプ政権でAIが著作者の許可なく音楽を学習材料に出来る法案が進んでいるが、この法案が通るとライセンシング契約は意味がなくなってしまうところを、技術的に阻止できる大きな役割を果たすだろう」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
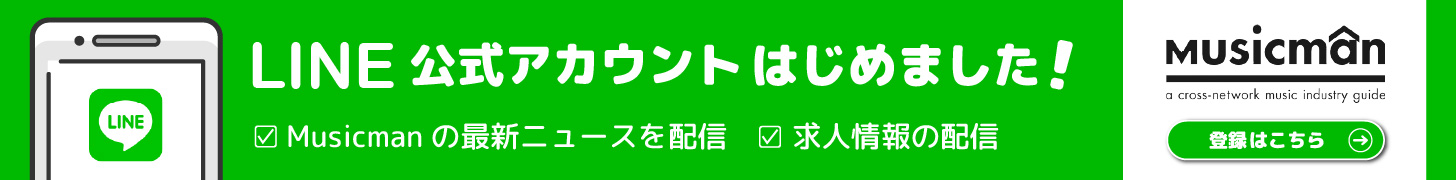
広告・取材掲載