【[韓国編]CEIPA × TOYOTA GROUP共創プログラム】ヒットソングライタージェイデン・ソン氏が語る韓国プロモーション

「CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Professional Seminar Public Series 1st Edition (韓国編)」が7月22日にトヨタ・東京本社にて開催された。CEIPAとトヨタグループによる共創プロジェクトである「MUSIC WAY PROJECT」の一環で、日本の音楽業界のグローバル展開支援・若手育成を目的としたものだ。セッションの中からMusicmanでは「Market Deepdive #1 (韓国編)」と題した、韓国市場のエキスパート3名による登壇内容を順次公開予定である。この記事では、グローバルな音楽ストラテジストであり、ヒットソングライターであるHYPEER Ink.代表のジェイデン・ソン氏のセッション内容を記事化する。韓国プロモーションにおいて「ハイパーファンダム」がキーとなることや、具体的なプラットフォーム戦略、ケーススタディについて盛り込まれている。
(2025年7月22日 於:トヨタ東京本社 B1F大ホール 取材・文:Musicman編集長 榎本幹朗、Musicman 山内千秋)
- 現在の韓国は、2011年頃の日本におけるセカンドジェネレーション韓流ブームに似た状況
- 5段階の韓国ファン層モデル・ハイパーファンダムがキー
- 韓国プラットフォーム戦略は「YouTube」「Instagram」が重要
- アーティスト参入ポジショニングのフレームワークを実践
- まとめ:3つの成功要因
現在の韓国は、2011年頃の日本におけるセカンドジェネレーション韓流ブームに似た状況
韓国マーケティングに関して最も多く受ける質問は「いくらですか?」だという。どの程度韓国マーケティングに投資すれば、どの程度のリターンが期待できるのか。この根本的な疑問に答えるため、韓国市場についてと、ファン層モデルを理解した上での戦略的なアプローチを体系化して説明した。
現在の韓国は、2011年頃の日本におけるセカンドジェネレーション韓流ブームに似た状況だという。韓国人がJ-POPというジャンル自体にファンとなり、興味を持つ段階を経て、さらなるJ-POPブームが始まっている。かつては YOASOBI のようなアーティストが来韓すると「こんな機会はめったにない」とチケットが即完売していたが、今では多くのJ-POPアーティストが韓国でライブを行う状況となり、チケットのインフレーションが起き始めていると話す。
この背景には、J-POPジャンルの中でまさに自分にとっての「推しの子(推し)」を探している熱心なファンの存在がある。K-POPジャンルを受け入れた人たちが、今度は日本の音楽ジャンルを受け入れ、「自分の一番好きなアーティストは誰なのか」を見つけようとしている状況だ。これから話す「差別化・ブランディング・マーケティング」は絶対的なものだと確信している。
5段階の韓国ファン層モデル・ハイパーファンダムがキー
韓国のリスナーシップを以下の5段階に分類し、それぞれに対応したマーケティング戦略の重要性について説明した。
1段階:ジェネラルリスナー(一般人層):アーティスト名、レーベル名を知らない層。知り合いから名前を聞いたことがあるという程度の経験や、ビジュアルアセット(MV、アルバムジャケット、ムードフィルムなど)がストリーミング開始のトリガーとなる。
↓
2段階:ライトリスナー:自分のお金は出せないが、無料で提供できる時間を投資してコンテンツを消費する層
↓
3段階:ヘビーリスナー:プロシューマー(プロデューサーとコンシューマーの役割を同時に果たすファンダムのこと)。オフィシャルアセットを二次創作し、SNSでシェアし、グッズ購買も活発
↓
4段階:ロイヤルリスナー(ロイヤルファンダム):アーティストの成功を自分の成功と捉え、アンバサダー的活動を行う
↓
5段階:ハイパーファンダム:ロイヤルファンダムの上位7〜10%のファン。1日に平均25.6回以上楽曲を再生し、月78回以上のエンゲージメントアクション(コメント、シェア、ライク)、オフライン参加率60%以上という定義で、アーティスト収益の大部分を担っている
グローバルマーケティング、特に韓国でのマーケティング戦略において最も重要なのは、この「ハイパーファンダム」をどう増やすかであると話す。もちろん段階ごとに個性があり、必要なプロモーションは異なる。それぞれに必要なプロモーション内容が話された。
韓国プラットフォーム戦略は「YouTube」「Instagram」が重要
2025年現在、韓国の音楽プラットフォーム利用状況は3年前と比較し大きく変化している。以前はMelon、genie(メロン:韓国最大級の音楽ストリーミングサービス/ジーニー:Melonに次ぐ韓国最大級の音楽ストリーミングサービス)中心だった韓国市場において、今や2人に1人がYouTubeで音楽を聴いている状況だ。Instagramも2,644万人(韓国人口約6,000万人の3分の1以上)が利用しており、情報収集の主要プラットフォームとなっている。
この2つのプラットフォームを中心とした「ローカルブレイキング」が韓国マーケティングの核心だ。日本のアーティストの特徴(1.フロントに出るアーティストと匿名で活動するネット系アーティスト、2.日本楽曲ならではの日本語中心の楽曲など)から「トラックブレイキング」と「アーティストブレイキング」の2つのアプローチに分けて戦略を立てる必要があり、この2つが合わさり「ローカルブレイキング」となると話す。
アーティスト参入ポジショニングのフレームワークを実践
以下の3つの要素からなるアーティスト参入ポジショニングのフレームワーク実践を提案している。
(1) ポジショニング:アーティストが韓国でどのような位置にいるかの把握
Leinaさんの事例では、YouTube Musicで何がお勧めされるか、自動生成される、パーソナライズされた”ミュージックステーション(日本語名:「ラジオ」機能)”を参考に、近いアーティストを知れる。
こういったポジショニングマップの作成が(HYPEERでは)可能であるが、共通点のあるアーティスト軍の活動指標、チケットパワーの調査ができる。発売前フリープロモーションはいつから始めたかなど参考にできる。
(2) カルチャーコード:韓国でトレンドとなっているカルチャーを自分たちのブランディングやメッセージにどう連携するか
実践的なプロモーション手法について。シーディング戦略:MVのハイライト部分や公演映像に日本語と韓国語の字幕を入れ、口コミマーケティングを促進
韓国では「ウェブジン」(ウェブのマガジン)が流行っている。@EYESMAG、@FASTPAPERMAG、@DAILYFASHION_NEWS、@JPOP_OZEなど。これらを利用したオーガニックプロモーションの実施。
2時間ほどのYoutubeプレイリストを活用したミュージックキュレーションが流行。コメント欄の行動力が高く、プレイリストリスナーの中でコミュニティが形成されている。
(3) チューニング:既存のマーケティングプランにカルチャーコードとポジショニングの結果を反映するか
キャンペーンをいつ、どのタイミングで入れるのかが重要。イベントやオンラインイベントを戦略的に出す。
まとめ:3つの成功要因
(1)グローバルマーケティングとは、バイラルではなくマルチローカライゼーション:国ごとに異なる戦略が必要。市場ごとに成功の法則は異なり、成果は決して直線的には拡張しない
(2)一夜の成功は、常に積み重ねの上に成り立っている:長期的な計画なしに、短期的な成果は決して持続しない
(3)重要なのは「何を聴かせるか」ではなく、「どう感じさせるか」である:音楽マーケティングの本質は、感情に響くことにある
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
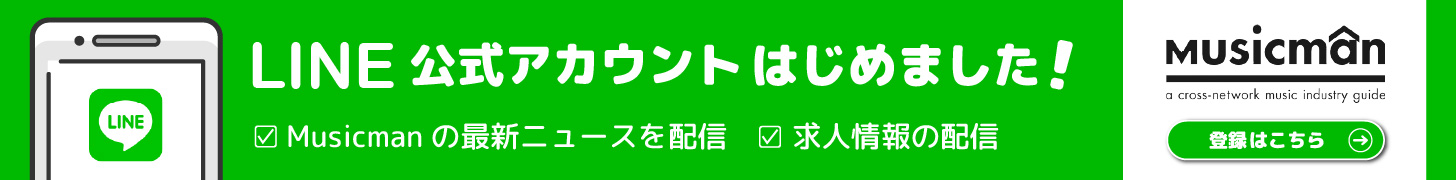
広告・取材掲載