【全文掲載】AIで作った音楽は人を魅了するか。Velvet Sundown騒動【榎本幹朗のMusicman大学#6】
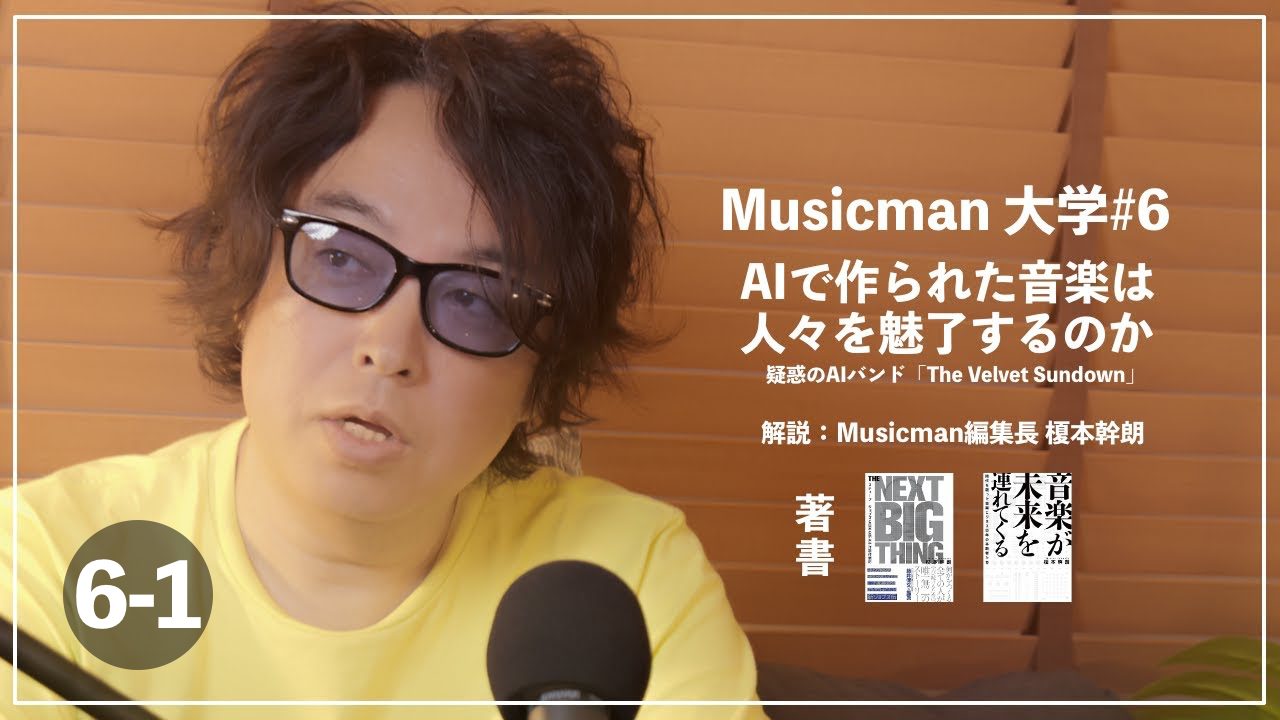
Musicman大学アーカイブはこちら
■お騒がせAIバンド
MC Tama:音楽業界の今を知りたいすべての人へ。音楽業界の最新動向を深掘りする、ミュージックマン大学。講師は「音楽が未来を連れてくる」「THE NEXT BIG THING」の著者として知られ、ミュージックマン編集長でもある榎本幹朗さんです。よろしくお願いします。そして、MCはTamaです。今日は「AIと音楽について」ということで、お話を伺います。
榎本:今日はまず聞いてもらいたい曲があります。
MC Tama:渋くてかっこいいですね。今日は音楽と生成AIについてのお話ということですが、この音楽とどう関係があるんですか?
榎本:実はこれ、生成AIで作った曲なんです。このボーカルも演奏も含め、全部です。「The Velvet Sundown」というバンド名で、Spotifyで見ると106万人の月間リスナーを獲得しています(7月7日収録)。ここ1ヶ月ぐらい急に話題になっていて、話題になったのは2つの理由があります。ひとつは、普通にいい音楽だということで伸びてきた。もうひとつは、世界的な音楽誌「ローリングストーン」が取り上げて、そのインタビューでのやり取りが物議を醸したということです。
ミュージックマンで公開した記事のタイトルは「1月でリスナー50万人超えのバンドに「AI疑惑」広報担当者が、AI音楽生成プラットフォーム「Suno」の限定的使用を認める」。広報担当者であるアンドリュー・フレロンさんという人が、「これSunoじゃないか?」という疑惑に対して「ローリングストーン」に答えたんです。Sunoってご存知ですか?

MC Tama:耳に挟んだことはありますね。
榎本:ミュージシャンやアーティストの方は、よく知っているかもしれません。Sunoは音楽生成では最もクオリティが高いと言われています。クオリティが高い理由は、もしかしたら著作権のある音楽を学習させているんじゃないかと疑惑が立つほどです。実際、裁判になって、著作権のあるコンテンツを学習させていたことを認めて謝罪しています。そのSunoを使ってアルバムを作っていたということです。
■AIで作った曲は創作といえるのか
「けしからん」かどうかという話になるんですが、Sunoはプロンプトで出力できるんですね。例えば「J-POPでYOASOBI風、BPM110ぐらいで、5月の雨上がりの渋谷みたいな雰囲気で音楽を生成してみて」と文章を入力すると、それっぽい曲を作ってポンと作ってくれる。
画像生成AIが出てきたとき、「もうイラストレーター廃業です」とよく言われましたよね。同じようにミュージシャンも廃業になってしまうのではないかと音楽でも言われたんですが、結論から言うと、実際はそうなってないんです。もう3年間ぐらいやっていますが。
実際の使われ方を見ると、バッキングをやってもらったり、コーラスをつけてみたり、曲作りの最初のブレーンストーミングでアイデアを出すのに使ったりして、「ちょっと違うな。俺だったらこうしたい」みたいな感じで、ツールとして使われているんです。
The Velvet Sundownの場合も、アルバム全部をAIで丸投げしたわけじゃなくて、AIで出力したものを編集したり、「こういう方向で」「Aメロの後、Bメロはこんな雰囲気でやってみて」みたいな指示を出しているようです。そこに自分の演奏をかぶせていったりしたら、これってもう創作活動なんじゃないかということです。
ディレクションしているわけで、全部やってもらうわけじゃない。自分も演奏するし、それをヒントにBメロを構成していく。これって楽器に近いですよね。
MC Tama:確かにそうですね。

榎本:あるいはアレンジャーさんを雇うのと同じです。アレンジャーに「こういう方向で」と依頼して、戻ってきたアレンジに対して「もうちょっとこういう感じで、あの曲っぽい感じでやってもらえますか」と指示を出す。ミュージシャンがそれをやっている場合、これは創作活動で、その一部になっているという考え方もあります。
ただ、問題になるのは、AIの学習元になっているデータがプロのミュージシャンが作った楽曲ベースになっている場合です。プロのミュージシャンたちが頑張って作った膨大な楽曲があるからSunoが優れたクオリティで楽曲を生成できるのに、その人たちに対価が還元されないわけです。
MC Tama:確かに。
榎本:それは問題なんですが、創作活動として見た場合、いろんなプロンプトを試して、自分の演奏も混ぜて、編集もして、方向性がずれてきたら指示も変えるというのは、いわばクリエイティブディレクターをやっているということ。自分の演奏も入れているので、これは創作のためのツールなんじゃないかと。
The Velvet Sundownの音楽はAIで作っているけれど、「AIで作っているからダメ」と本当に言えるのかということになると思います。
簡単に言えば、漫画を描くときに背景をAIに任せたら楽になりますよね。ただ、問題が起こるとしたら、その背景がいろんな既存の著作物を学習させていて、ほとんどパクリに近い形で出てきたらまずいということ。同じことが起こっている可能性があります。
AIにプロットを考えてもらって、「これいいけど、もうちょっとこうしたいな」とブレーンストーミングに使っているなら、それは「AIに丸投げしただけ」とは言えない。問題は、AIに丸投げするかどうか。あとは、AIが作ったところが著作物ベースになっている可能性が非常に高いので、実際にそういう裁判が起こって、AI側も使っていることを認めています。そこが問題になるんです。
MC Tama:だから、AIに学習させた元のアーティストや作品に対して、どう還元していくかが課題になるんですね。
榎本:そうです。
■二転三転してバンドはAI使用を認めた
そしてこの騒動は、ちょっと複雑で急転直下が連続して起こって盛り上がったんですが、時系列を整理して説明しましょう(8月11日追加収録)。
まず、The Velvet Sundownは6月5日に「フローティング・エコーズ」というアルバムをSpotifyに出しました。その15日後に「ダスト・イン・ザ・ウィンド」という2枚目のアルバムを出した。15日で2枚目ですよ。
そもそもSpotifyのプロフィールが、まさに生成AIですと言いたくなるようなアーティスト写真で、ジャケットもそういう感じ。ChatGPTで書いたような非常に機械的なプロフィールになっていて、「これAIじゃないか」と。
見た目からして、文章を読んでも、音楽を聞いても「これSuno使ってるんじゃない?」という感じでした。ドラムにSuno特有の音の薄さがあったり、ボーカルにSuno特有のちょっとした揺れがあったり。僕が全部聞き分ける自信はないんですが、専門家と呼ばれる人も言い出して、ざわざわしてきた。
6月26日にある業界誌が、「疑惑のあるThe Velvet Sundownがネットで話題になっている」と取り上げました。それでまた盛り上がってきて、リスナーから「これ、AIなんじゃないですか?」と聞かれるわけです。ただ、The Velvet Sundownは「AIは使っていません」と答えていました。
決定的だったのが7月2日、「ローリングストーン」がこの話題を取り上げて、プロフィールに書いてあったアンドリュー・フレロンという人にコンタクトを取って、「AI使ってるんですか?」と聞いたら、「はい、実は使ってるんですよ」と。「じゃあ、なんでバンドはAI使ってないって言ってたんですか?」「それはこうでもしなかったら、みんなThe Velvet Sundownなんて聞かなかったでしょう。こうやって話題になったから、AI じゃないかって聞いてくれたんじゃないですか。これの何が悪いんですか」と言い出したんです。
MC Tama:すごいですね。
榎本:マーケティングのためだと。「私は自分のことをアート・ホークス(アートの詐欺師)だと思っている」と完全に開き直って説明した。それを世界的な音楽メディアが載せたものですから、また大騒ぎになって、The Velvet SundownのSpotifyリスナー数が100万人を突破しちゃったんです。
結構な騒ぎになって、いろんなメディアもこれを取り上げることになりました。当然うちミュージックマンも「世界にはこんな人がいます」って載せたんですが、そしたら翌日、フレロン氏がMediumというブログサイトに「実は俺はThe Velvet Sundownとは無関係で、広報担当者って書いたけど、そうじゃない。そもそも俺がThe Velvet Sundownの広報だって、あなた方がファクトチェックしないで勝手に決めつけただけ」と言い出したんです。
「実は俺のところにもそうそうたるメディアが取材依頼に来てると。フォックスとかバラエティとかワイヤードとかビルボードとかテッククランチとかみんな来てるけど、あんたたちジャーナリストって名乗ってるけど、俺のこと本物って確認したの?」ということを言った。
「ローリングストーン」は載せざるを得ないので、「フレロンという人は実は広報とは関係なかった」と。The Velvet Sundownも自分のXで「フレロンという人は広報として記載されていたけど関係ありません」と。

MC Tama:その人は何者だったんですか?
榎本:それは分からないですね。なぜかというと、その後も動きが怪しいんです。自分は偽物だと言い出した3日後に、Spotifyのプロフィールでバンドがこっそりプロフィールを変えちゃったんですよ。
どう書いたかというと、「このプロジェクトは、AI時代における著作権、アイデンティティ、そして音楽そのものの未来の境界を問い直す、継続的な技術的挑発です」と。つまりAIを使っていたことを認めちゃったんです。
やっぱりAI使ってるじゃないかと、二転三転しているわけです。短期間の間にすごい展開でした。
■音楽産業のトップまで波及したが音楽自体の評価は?
これだけでは終わらなくて、この話が業界のトップまで行っちゃった。イギリスのBPI(日本のレコード協会にあたるところ)の偉い人が、このThe Velvet Sundownの騒動を受けて、「AIだけで作った曲はちゃんとそういうふうにSpotifyとかで表示してほしい。これから世の中はそうなっていくべきだ」とコメントを出すぐらい、業界協会のトップまで話が行きました。
偶然だと思うんですが、そのコメントを出した日に、バンドがその後2枚のアルバムを続けざまにリリースしたんです。Spotify上で。そもそもこんなスピードでアルバムって作れるのかというのが、6月の段階で起こっているわけです。最初の2枚は溜め撮りしていた可能性があるけど、そこから1ヶ月でまた2枚を出してくると、これはAIだけで作っているんじゃないかと当然思われる。
実際、Spotifyがアルバムの1枚と、複数の他の曲を削除しちゃったんです。SpotifyはAIを一部使っているもの、楽器みたいに使っているのはOKだけど、まるっとAIで作ったものはダメという方針なので、「やっぱりAIで全部作ってたのね」という傍証になりました。
その後一番伸びた、最初に聞いてもらった「ダスト・イン・ザ・ウィンド」は結局、今見ると239万再生。この騒ぎの割には、そこまでという感じです(8月11日時点)。音楽自体は、聞いてもらったと思いますが、確かに人間が作ったのかAIで作ったのか分からない、それくらいのクオリティなんですが、音楽として面白かったかというと、そうでもなかった。心に響いてなかったというか、話題騒ぎが起こって終わっちゃったという感じでした。(「お騒がせAIバンド「The Velvet Sundown」、Spotifyのリスナー急減」)
これに関して、国連のレベルまで行っちゃって、国連のAIサミットでユニバーサルミュージックの偉い方が基調講演したんですが、そこでThe Velvet Sundownの話題が出て、マイケル・ナッシュCDO(チーフデジタルオフィサー)がコメントを出したんです。
「いろんな報道で露出したおかげで100万人のリスナーとか獲得してるけど、月間100万で、再生数も100万、それじゃあチャートインはできませんよね。AIってだいたいそのくらいなんですよ」という趣旨のコメントをしました。
僕も同意見なんですね(続く)。
Musicman大学アーカイブはこちら
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載