【全文掲載】日本の音楽業界はピンチ(チャンス)MUSIC AWARDS JAPAN解説【榎本編集長のMusicman大学】
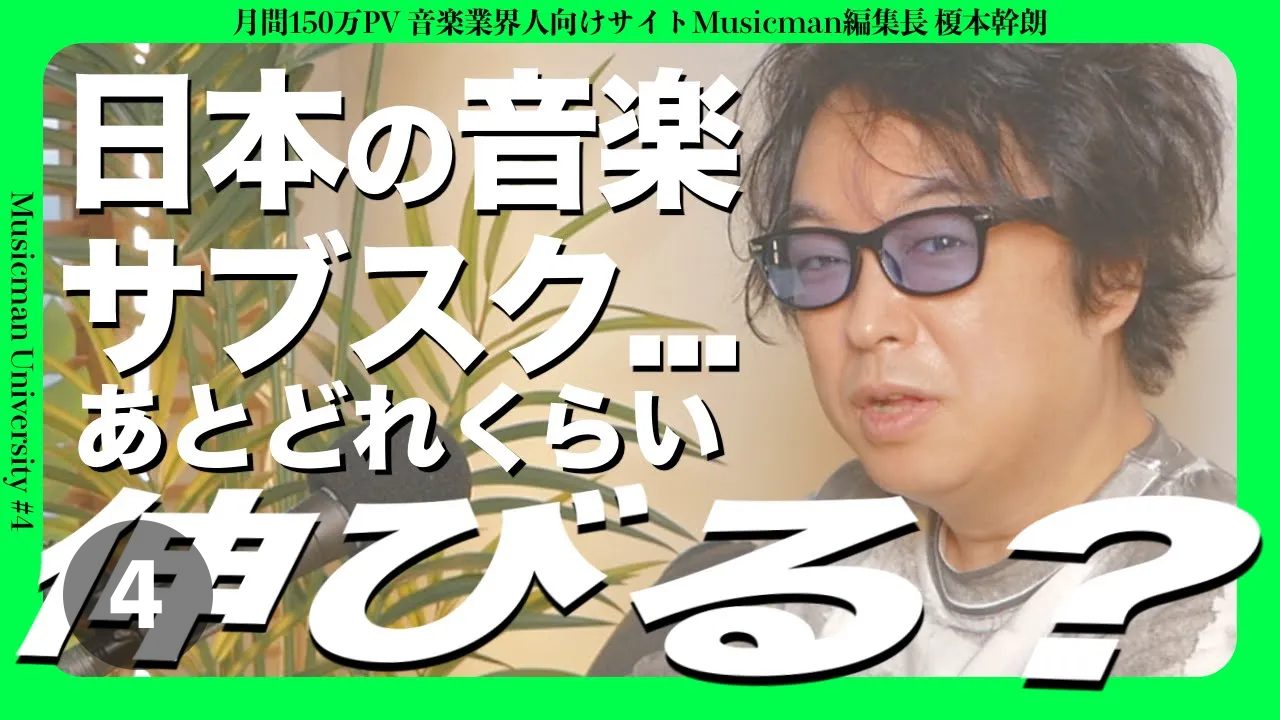
MC:Tama: 今日(6月2日)のテーマは何でしょうか?
榎本: 今日は5月21日22日に京都で音楽の祭典MUSIC AWARDS JAPANについてお話ししようと思います。
MC:Tama: 京都で行われたんですね。
榎本: はい。NHKとYouTubeで生中継されたんですけど、Tamaさんはご覧になりましたか?
MC:Tama: 見てないです。
榎本: 見てないですか?残念ですね。評判良かったんですよね、Xとかね見てると。最初は「レコード大賞みたいなやつがもう1個出てきて、なんか意味あんの?」みたいなネガティブな意見が多かったんですけど、実際見てみたら素晴らしかった。僕も実は招待されてその場で見てたんですけど、音楽賞イベントであんなに楽しかったのは初めてでした。
MC:Tama: いいなぁ私も行きたかったなぁ。
榎本: ちなみに最終日に僕いて、「Top Global Hit From Japan」がYOASOBIの「アイドル」、最優秀ニューアーティスト賞がtsuki.っていう高校生の女の子ですけど、最優秀楽曲賞がCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」。もうCreepy Nutsはもういろんな他のショーもそうなめしてたんで、ヒップホップブームを日本でもう一回作っただけじゃなくて、「世界でJ-POP始まるか?」みたいなところで、もう先陣を切ってる。あともう一つ最優秀アジア楽曲賞っていうのがあって、これアジア日本に限らずアジアのアーティストさんで素晴らしかった国際的な賞を目指していて、aespaの「Supernova」が決まった。そういう感じでしたね。
MC:Tama: 榎本先生、MUSIC AWARDS JAPANこれはどういったアワードなのか、今まであったレコード大賞とかとどういったところが違うか、ちょっと私わからないんですけど教えてください。
榎本: そうですね。僕らも開催の1年前に最初に説明を受けた時に「何が違うんですか?」って質問したんですけど、まずオールジャパンでやってます。オールジャパンっていうのはレーベルが集まっている日本レコード協会、音楽事務所が集まっている音制連、芸能事務所の音事協、音楽出版が集まっているMPA、あとコンサートプロモーズ協会。
今J-POPのアーティストさんがようやくTikTokとかYouTubeとかNetflixのアニメとかを使って、ようやく世界で広まりだしてるんですね。実際にグラミー賞を主催しているレコーディングアカデミーが今年1月、これをうちが記事にしたんですが(「「2025年はJ-POPが世界的ブームに」 レコーディングアカデミー、音楽トレンド5つを予測」)、「今年はJ-POPがブームになる」と。「今までK-POPのブームとかあったように、J-POPのブームがいよいよ始まる」っていう記事を出し始めてて、それだけの根拠があるデータって出てるんですよ。
Billboard JapanもGlobal Hits Songs exc. Japanっていう、つまり日本以外で聞かれてる世界で聞かれてる日本の音楽のチャートを作って、毎回一周更新してるぐらいもう広まりだしてるんですね。
その時に例えばアメリカだったらグラミー賞とかあるいはMTVやってるビデオミュージックアワーズとか、いろんな賞があります。賞を取っていると、それを肩書・名刺にして、ワールドツアーを組めるとかいろんなことができるんですけど、日本人はそういうのは何もない。「世界に出てくって言っても、何の名刺もない。これ作ってあげないと」っていうことで始めたのがMUSIC AWARDS JAPANです。
MC:Tama: 「どこがすごい?」っていうのがありますか。
榎本: 去年ですね、秋にMUSIC AWARDS JAPANを開催するっていうのをようやく公開できたんですけど、その時にXでポストしたらバズったんですが、まず選出方法がすごいです。それはエントリーとなる曲、ものすごい数あって僕もね1日だけ聴ききれなかったんですけど、それくらいありました。
それが誰かが作為的に、これをエントリーこの曲を候補にしちゃうと、でもその候補の段階でバイアスかかっちゃうじゃないですか。それじゃ納得いかないでしょうと。それをデータをベースに自動で選出してしまう。Billboard Japanとか。Billboard JapanはSpotifyとかYouTubeのデータを元にできてるんですけど、それとかオリコンはCDのデータとか、最近だとストリーミングのデータもオリコン反映してますけど、あとGFKとかですね、そういう音楽データを扱っている会社があって、そこのデータ使って自動的にエントリー作品を選ぶ。作為がない。
あともう一つが審査員がすごい。審査員がこういう偉い人が審査員だからすごいってわけじゃなくて、音楽業界もほぼ総出で、5000人審査員。
MC:Tama: 5000人?
榎本: はい、すごいですね。いわゆる僕らみたいな音楽業界人だけじゃなくて、アーティストさんとかクリエイターさんとかエンジニアの方とか音楽ビデオのディレクターさんとか、コンサートプロモーターとかそういう現場でも活躍されている方も入った5000人です。この方で選んだ。3つ目が先ほど言ったように主催団体がすごいです。特定の団体特定、レコード会社の利益のために作ったものではない。もう全日本でやっていこうと。本気で日本の音楽を輸出するために始めたというところが今までとは違う。
だからこそ、オールジャパンで集まってやらなきゃいけなかった。このタイミングでこれをやるんだったら、どこか一つの会社が頑張るとか、一つの団体が頑張る、日本の音楽は輸出しきれないんで、みんなでやることになったってことですね。
MC:Tama: なんで5月というところで行われたんですか?
榎本: そうですね。12月とかね、紅白とか、レコタイのあたりにああいう音楽の祭典をNHKが中継するっていうので、そういうあたりじゃないのっていう疑問の声もあったんですけど、これは今言ったように、日本のアーティストさんに世界で通用する名刺を作るためにやってることであって、これ後で説明しますけど、これね綺麗事じゃなくて、本気でやらないとまずい状況なんですよ。
あるいは本気でやったら今チャンスがある状況にようやくなってるんで、その名刺を作るためにやってるんであって、新しい賞を日本で作るためにやってるわけじゃないんです。紅白に対抗するため、レコード大賞の代わりになるものを作りたいからやってるわけじゃないんで、それもあって、5月という京都になったんですけど開かれることになったと思います。
MC:Tama: 榎本先生、今回ちなみに京都は行かれたんでしょうか?
榎本: 招待されて行きました。
MC:Tama:私も行きたかった。
榎本: 善処します(笑)。さっき冒頭でも喋ったんですけど本当にお世辞抜きで素晴らしいまとまりというか本当、豪華でしたからね。
例えばこれ、紅白の悪口言うんじゃないですよ。紅白ってやっぱりすべての年齢層に納得していただくためにブッキングしている。いっぽうでMAJは聴かれてるデータを元に自動でエントリー曲決めて、アーティストさんを含めた5000人が選んでるんで、MUSIC AWARDS JAPANは本当に音楽ファンの再生数を稼いでいて、プロの5000人が素晴らしかったっていうのを選んでいるんで、そういう完全に純粋に音楽でブッキングしたんで。
僕もインタビューさせてもらったんですけど、テレ朝のミュージックステーションの利根川プロデューサーっていう方が総合演出をなさってたんですけど、放送はNHKだったからそこだけ見ても分かる通り本当に業界の垣根を超えてやってたんですよ。非常に素晴らしい演出をなさってて、素晴らしいものになってたと思いますね。
MC:Tama: 見てみたかったなぁ。いい経験されましたね。
榎本: そうですね。それも第1回行ったっていうのはね、ジジイになったらね、孫とかひ孫に自慢してやろうと思ってるんですけど、きっとNHKで、その頃もやってると思うんで。
MC:Tama: 第2回は私も一緒に参加させていただきたいと思いますので、屋代社長、よろしくお願いいたします。それで今回ですね、このMUSIC AWARDS JAPAN、ヤフーニュースの方でも取り上げられていて、「日本の音楽シーンにどのような影響を与えると思いますか?」という記事が上がっていたんですが、そのアンケートの中で「全く影響を与えないと思う」67.5%という数字があったんですが、これ何でだろう?ってちょっと疑問に感じたんですけど。
榎本: そうですね。これあの質問の最初に「ミュージックハウスジャパンは日本の音楽を世界に広めることを目標にとして開催されています。あなたはこのアワードが日本の音楽史にどんな影響を与えると思いますか」ってなってるんですけど、それでも否定的な意見が多かった理由が2つあると思うんですけど、まずそもそも冒頭で説明してるんですけど、日本の音楽を世界に広めるためだっていう、日本の音楽シーンをそのもののためにやってるわけじゃないんですよというのがピンとこなかった。日本の音楽シーンを世界に広げるためにアーティストさんを輸出するために、日本の音楽シーンをちょっと広げるためにやってるわけではない。
もう一つがそもそも「日本の音楽が世界に広めるって綺麗事じゃないよ本気だよって言っても、そんなこと本当に起こるの?」っていう、そういう気持ちが強く出ちゃったんじゃないかなっていう感じですね。
MC:Tama: まあ1回目ということもあったので、やっぱり世間一般的にはそれがまだ認知されていないということなんですかね?
榎本: というか、日本の音楽業界がこんだけまとまったのは史上初だと言ったんですけど、それには強い危機感もあるし、いよいよ日本音楽を出せるチャンスも感じているんですね。
MC:Tama: ピンチとチャンスっていうのは具体的にどういったことなんでしょうか?
榎本: 日本の音楽産業って今ピンチとチャンスが両方来てるんですよ。まずピンチの方について話すと、後でグラフ出しますけど、世界の音楽売上の推移っていうのはV字回復してるんですね。それは2つ理由があってまず1つはCDがダメになったんですけど、スマホの普及のおかげでサブスクで稼げるようになった。音楽ソフトが伸びるようになって。もう2つ目はサブスクと関係するんですけど、先進国以外に新興国と呼ばれる皆さんが音楽にお金を払うようになったんです。サブスク経由で。それがあってどんどんどんどん伸びてVGで回復しています。
ひるがえって日本の音楽売り上げってどうなってるかっていうと下げ止まりました。で上がってくるのかなと思ったら上がらないんですね。ずっと上がらないまま進んでて、これがピンチ。まあサブスクはあの広げていくんですけど、それだけじゃ広まらないぞと。でそもそも日本って少子高齢化がどんどん進んでますからね。で音楽ってやっぱり20代30代が中心なんで、どうしてもメインのっていうわけですよ。
これから実際にこれもここに出してますけど、レコ協がほぼ毎年、音楽メディアユーザー実態調査っていうのをやってるんですけど、ここに最近よく質問されてるのが音楽、そもそも興味ありますか?お金払って聴きますか?無料だったら聴きます。でも無料で聴くんだけど、知ってる曲しか聴かない。あとそもそも音楽興味ないですっていう、この4つの説問を設けたんですけど、10年以上前、サブスクが始まる前っていうのは無料で聴く人ばっかりになって、これ問題だねっていうことになってたんですよ。
サブスクとスマホを使ったらこれ有料で聴いて、もう1回聴いてもらえるようになるんじゃないかと。それもあんまりうまくいってないんですけどね。由々しきことが起こってて、そもそも音楽に興味ないですっていう人がどんどんどんどん増えちゃってて、このデータだと、2012年は無関心層が16.2%だったんですけど、2024年は46.4%。ほぼ半分「もう音楽に興味ないっす」ってなっちゃってるんですよ。
MC:Tama: なぜ?
榎本: なぜっていうのがですね、2つ思いつくと思うんですね。1つはさっきの少子高齢化。まあ音楽ってやっぱり若い時に興味あって結婚して、子育て始まったあたりで男女ともに音楽離れて送るんですけど。
MC:Tama: 私ですね。
榎本: 俺もね35くらいの時にいったん音楽離れしかけたんだけど、その頃に2009年くらいかSpotifyとか、Pandoraとかね見つけて「すげーこれは!音楽聴き放題楽しい」ってなって、また音楽聴くようになって、それを広めてやろうっていうんで、このミュージックマンで2012年から連載して「これからSpotifyとか音楽サブスクが来ますよ」っていうのを僕は旗振り役やってたんですけど、この年代別の構成費っていうのをデータね、ここに出しますけど、まず音楽の無関心な層っていうのが2022年の大学生25.9%だったんですよ。
それが2024、去年31.6%に上がった。20代と40代もこれは高止まりしてます。20代が2022年が42.7%無関心、それが2024年が43.2%無関心。30代が46.6%、3年前が、2022年が2024年が44.7%と高止まりしてるんですけど、どんどん興味がなくなってる。多分大きな理由は音楽以外の娯楽がすげえ増えちゃってるんですね。やっぱり今YouTubeとかでいろんな動画が見れるので、興味のあるものが分かれてるんですね。
そうですね。TikTokとか見てたら女の子だったら、お化粧の仕方とかファッションとかそっちがどうしても目に簡単にいっちゃうし、男の子だったらゲームとか、アニメとかにいっちゃうんですよ。スマホの中での目の取り合いっていうか、耳の取り合いになると、どんどん音楽の比率が下がっているっていう状況があります。
MC:Tama: 今、ピンチという話を聞いて「え?」と思ったことがたくさんあったんですけど、チャンスというのはどういったところでしょうか?
榎本: これはJ-POPが特になんですが、コロナ禍の間に皆さん活動の場がデジタルしかなくなったんで、TikTokやYouTubeで活動する場もそうだし音楽ファンなりエンタメ娯楽を楽しむ人がスマホを見るしか、コロナの時なかったんで、その時からTikTokやYouTube経由でJ-POPがバズるようになったんです。
そのあたりからですね、2つの流れがあって一つはやっぱりアニメがNetflixやアマプラを通じて世界的に見てもらえるようになった。向こうでもやっぱアニメってオタクのものだったのが、一般の人も楽しめるようになった。特に進撃の巨人が大きかったかなと思ってるんですけど、大人も楽しめるクオリティだったんで、推しの子でYOASOBIさん、鬼滅の刃でLISAさんとか、そういう風にアニメ経由で出るようになったし、あとはアニメとも関係なく、TikTokやYouTubeを通じて世界的に聞かれるようになったんですよ。藤井風さんの「死ぬのがいいわ」とか、さっきのCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」とかどんどん行くようになって。
日本のJ-POPのシェアって今どれくらいあるのか、ちょっとね今っていうのはデータ持ってないんですけど、去年のLuminateっていう、Billboardにデータを提供してる会社あるんですけど、そこが出したデータ、これもあの僕らが記事化(「J-POPの国別需要が明らかに アメリカ1.9% 台湾8.5% 韓国4.0% 香港6.9%」)したバズったんですけど、国別のJ-POPの需要っていうのがアメリカが1.9%です。で台湾が8.5%、韓国が4%ぐらいですね。で大体ね、これK-POPの3分の1ぐらいなんですけど、でも伸び始めてて、あと冒頭で言ったように、今年からJ-POPが来るぞっていうのは、レコーディングアカデミーが予想したりとか、火がつき始めた。
ちょうどK-POPが広まり出した頃と似てるぞっていう。K-POPは最初ドラマから来てその後音楽聴かれるようになって、BTSがとどめの一撃っていう形だったんですけど、そういう感じが多いんじゃないかと。日本の場合はアニメから始まって、でもアニメから独立したアーティストも出始めて、それが広まるんじゃないかっていうのが、アメリカの音楽業界も目付けを始めてるっていう状況で、つまり今までと違って、即世界に広がるようになったんですね。響くようになった。
データがたまると、さっき言ったLuminateっていうところか、そういうストリーミング世界中にしてるとね、この国でこの曲がこれくらい聞かれてってなって、このデータがある海外のツアーとかブッキングできるんですよ(「世界の音楽業界ではLUMINATEのデータが通貨になっている」その理由を訊いてみた)。データでこれくらい聞かれてるんだったら呼んであげようかとかなってるんで、あと名刺が欲しい。データとかね、難しい話じゃなくて、どういう賞を取ったんだと。
MC:Tama: なるほど。
榎本: その賞を作ってあげれば、もう生きる段階に入ったんじゃないかと。それをやれば、今国内の市場っていうのはもうシュリンクしちゃうはいするんじゃないかと言われてるんだけど、世界にちゃんと輸出していけんじゃないかっていうことで、これ大きな方向転換なんですよ。日本の音楽業界ってずっと世界2位の市場規模だったんですよ。音楽大国だったんで、日本国内向けにやっていくだけで十分だったんですけど、これをもう世界のマーケットでやっていこうじゃないかというのが、もうデータ的にもチャンスが出てきたし、社会の構造の変化っていうんですかね、ネットが普及でいよいよ生きるってことで、オールジャパンでやっていこうっていうことになったんですね。
MC:Tama: ということはもうMUSIC AWARDS JAPANってすごいアーティストにとっては、素晴らしい名刺になるはずですね。
榎本: 課題があるとしたら今言ったように、世界に通じる名刺にしなきゃいけない。「そのMUSIC AWARDS JAPANって何それ?」って海外の人がねなっちゃったら名刺にならないじゃないですか。「いやいや日本でこういうショーがあってですね」とか、今僕が解説したようなことを喋らないと「うーんそういうショーなんだ、ふーん」ってなんないと。だからそれが世界の音楽イベント世界のショーと、MUSIC AWARDS JAPANがしっかりとつながっている状態っていうのを作れば、ちゃんと名刺として通用するようになるんで、それが次の課題になるんじゃないかなぁと。
まだ初回ですから、MUSIC AWARDS JAPAN自体をまずやってみる。それを国内で広めるところでも、本当に大変なんですけど、まあでも次の課題として、そういうのが業界の共通認識としてあるかなぁと思っております。
今回2本撮りなんですけど、初めてアシスタントをついていただいてどうでした?僕の話伝わりましたかね?
MC:Tama: はい。MUSIC AWARDS JAPANが、そういったアーティストに対する名刺的なものを差し上げたい。世界飛び立つために、そういったものを差し上げたいということで作られた祭典なんだなということがすごくわかったことと、今回私の周りで知っている人がすごく少なかったんですね。
ただNHKで放送されたり、YouTubeで配信されたり、Yahooのニュースで取り上げられたり、この1年かけて、だいぶ認知度が一般的にも上がってきて来年どうなるのかな、すごく楽しみだなと思ったのと、あとこのMUSIC AWARDS JAPANがグラミーとか並ぶぐらいの、そういった祭典になるのが、私は楽しみだなって思いました。
榎本: そうですね。やっぱYouTubeの力が強くて、MUSIC AWARDS JAPANにノミネートされた曲っていうのは2割以上世界でのストリーミング数は伸びたらしいですね(【ビルボード・データ公開】5月のMUSIC AWARDS JAPANは確実に世界展開していた:海外ストリーミング31%増、藤井風は香港で爆伸び)。もう早速効果は出てるんで、どんどんこれから伸ばしていくために、皆さん応援していただけたらと。
MC:Tama:ありがとうございました。
プロフィール
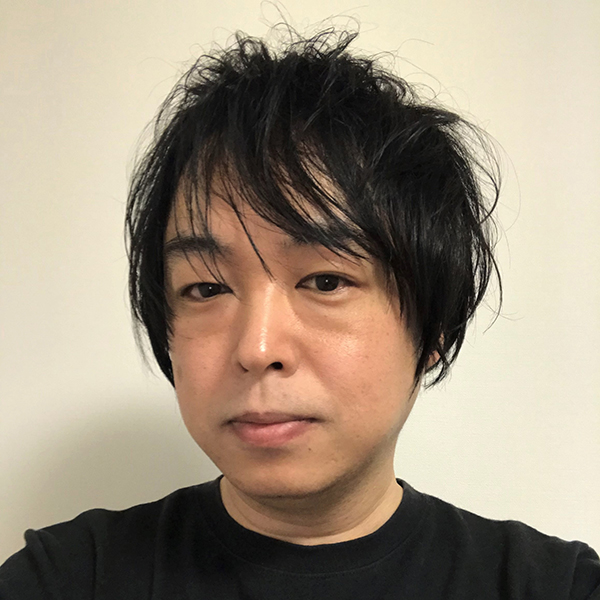
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。Musicman編集長・作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。著書に「音楽が未来を連れてくる」「THE NEXT BIG THING スティーブ・ジョブズと日本の環太平洋創作戦記」(DU BOOKS)。『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載。
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載