第198回 株式会社シャ・ラ・ラ・カンパニー 代表取締役会長 中曽根勇一郎氏インタビュー【後半】

今回の「Musicman’s RELAY」はリスペクトレコード代表 高橋研一さんからのご紹介で、株式会社シャ・ラ・ラ・カンパニー 代表取締役会長 中曽根勇一郎さんのご登場です。中学時代に洋楽に目覚めた中曽根さんは、自身で折れ線グラフをまとめるなど米英のチャートマニアに。大学ではブラックミュージックと一人旅に没頭し、その後、紹介されるまま始めたシャ・ラ・ラ・カンパニーでのバイトとしてラジオ業界へ。フリーでの活動を経て自身の会社を立ち上げ、当時無名だったやまだひさしさんと作り上げたTOKYO FM『ラジアンリミテッド』は一躍人気番組になりました。
しかし、好調だった自身の会社を解散した中曽根さんは1年間の世界旅行へ。帰国後、腰掛けのつもりで復帰したシャ・ラ・ラ・カンパニーで、その1年分の経験を放出。J-WAVE『MODAISTA』やジャイルス・ピーターソン『WORLD WIDE 15』など国際色溢れる番組を数多く手がけられました。現在は代表取締役会長にありながら現場に立ち続ける中曽根さんに旅のお話から、ラジオ番組制作の今後やポッドキャストについてまで話を伺いました。
(インタビュアー:Musicman発行人 山浦正彦、長縄健志 取材日:2022年10月31日)
▼前半はこちらから!
第198回 株式会社シャ・ラ・ラ・カンパニー 代表取締役会長 中曽根勇一郎氏インタビュー【前半】
「たまったお金は全部使ってやろう」会社解散後、1年間旅に出る
──中曽根さんはどうされたんですか?
中曽根:僕は丸1年、完全に仕事を辞めて、行ったことのない海外の国々を回わろうと思ったんです(笑)。
──1年間旅行ですか!? すごい・・・中曽根さんって一つのところに留まっていられない性質なんですかね?(笑)
中曽根:なんとか留まろうとするんですけど(笑)、やはり見たことのない世界を見たかったんですよね。それで、今でも売っていますけどエアラインの世界一周チケットというのがあって、今はもうEチケット化されちゃったんですけど、その当時はまだギリギリ紙で、それを買って旅に出たんです。
──いわゆる空の回数券みたいな感じ?
中曽根:そうですね。僕が買ったのはJALが加入するワンワールドというアライアンスのチケットで、まず日本からカンタス航空でオーストラリアへ行き、オーストラリアから南米方面に行って、南米ではランチリ航空、そのあとアメリカンエアに乗りアメリカ、ブリティッシュエアでヨーロッパ方面に向かい、最後はキャセイパシフィックでアジアから帰ってくるみたいな。ヨーロッパ内はどこにでも電車で移動できちゃうので、ユーレイルパスを買って動いていました。
──それをほぼ1年間。
中曽根:いやあ、本当に楽しかったですね(笑)。そのときの経験が今の自分の仕事のベースになっていますね。
──でも1年後のこととか特に考えず旅行していたわけですよね?
中曽根:そうなんです。もう放送の仕事をしなくてもいいやと思っていましたしね。あんな形で会社を解散しちゃいましたし(笑)、全然違う仕事でもいいなと思っていました。
──怖いもの知らずとも言えるし、大胆ですね。
中曽根:あのときは「たまったお金は全部使ってやろう」と思っていました。「貯金するのはまだ早い」と(笑)。
──(笑)。ちなみにどんなところに宿泊していたんですか?
中曽根:まだAirbnbとかありませんでしたから、ホテルに泊まることもあったんですが、メインは「留守の間に、私の家貸します」「私の家の空いてる部屋貸します」みたいなことが書かれた、Airbnbのはしりみたいな掲示板があって、その掲示板を常にチェックして「1週間後にそっちに行くので、その部屋を貸してもらえますか?」みたいなメールを出しては部屋を借りていました。このプロセスが意外と楽しかったんですよね。
──印象に残っている地域や家はありますか?

中曽根:ニューヨーク、ブルックリンの倉庫を改造したところですかね。当時のブルックリンのウィリアムズバーグはまだ倉庫地区で、アーティストっぽい連中が住めるように改造した倉庫に移り住んでいたんですよね。今はマンションばかり建つ高級エリアになっちゃいましたけど、その直前のちょっと危ない感じのエリアで、業務用のどでかいエレベーターに乗って部屋に入るんですが、体育館みたいにだだっ広い空間が4つの部屋に間仕切りされているんですよ(笑)。それで、こっちにはインドのやつがいて、あっちには北欧のやつがいてみたいな宿だったんですが、これが滅茶苦茶楽しかったんですよね。キッチンは共有で、お互いの国の料理を作る日が決まっていて、僕はそんなに料理が得意じゃないので、日本食の総菜屋でおかずを買ってきて適当に作ったフリはしていたんですけど(笑)。
──(笑)。バックパッカーみたいなレベルとはちょっと違うんですね。
中曽根:もうバックパッカーは卒業したと思っていました。ユースホステルとかにも泊まってないですし、普通の旅なんですけど、かといってしっかりしたホテルに泊まるのは「まだ早いな」という気持ちもあって(笑)。
──そういったホテルに泊まると旅人同士の交流もほとんどできないですしね。
中曽根:まあ1泊だけとかそういうときは「どうせ泊まるなら一番いいホテルに泊まろう」と思っていましたし、フランス、イタリア、スペインあたりにいたときは、ミシュランのガイドブックを片手に「星のついた店はどれくらい美味いのか確認しよう」と店を巡っていました。
──中曽根さんは食ベるのもお好き?
中曽根:好きですね。今の僕はベジタリアン気味なんですが、その当時はまだいろいろ食べていました。星がついている店というのはどんなものなのか? という好奇心もありましたし、「金は残さず使ったれ」と思って来ていますから、食べることにもバンバン使っていました。ちなみに今シャ・ラ・ラは放送事業と別会社で飲食事業もやっているんですが、そのベースはあのときの旅行にあったと思っています。
──そして、1年間旅行して帰国したと。
中曽根:帰ってきて特にやりたいこともなかったというか、仕事はなんでもいいような気もしていましたし、なんなら旅行で回ったところにもう1回行って仕事をするのもアリだなと思っていました。例えば、ニューヨークで仕事をするとライバルが多くて大変そうだけど、オーストラリアならのんびりしているし英語だし、街としてもシドニーやメルボルンはすごく気に入っていたので「オーストラリアもありだな」と思っていましたし、フランスにも友だちがいっぱいできましたから、彼らに「ちょっと手伝うから雇ってよ」というのも簡単だなとか、いろいろ想いをめぐらしながら日本に帰ってきたんですよ。
それで「どうしようかな」と思っていたところに、僕をシャ・ラ・ラに紹介してくれた児玉さん(六本木のバイト先の元店長)から連絡があり、実はその児玉さんはいつの間にかシャ・ラ・ラに入社して、佐藤社長の右腕になっちゃっていたんですが(笑)、彼が「お前帰ってきているんだったら、一旦挨拶しにおいでよ」と言ってくれて、それで佐藤社長に「戻ってきました」と挨拶したんです。それで別になにも起きないはずだったんですが、児玉さんが「色々やりたいこともあるかもしれないけど、ブランクがあった放送業界がどうなっているか、ちょっとだけ見てみたら?」って声を掛けてくれたんです。
1年間の旅行の蓄積をアウトプット〜ジャイルス・ピーターソンとの出会い
──なかなかいい言葉を掛けてくれましたね。
中曽根:それで「じゃあ、ちょっとだけ」と、腰掛けの社員にはならないスタンスでシャ・ラ・ラの仕事の手伝いをすることになったんです。ただ、ちょっとした手伝いと言っても、いざラジオ番組の制作現場に身を置いたら、1年間の旅行で蓄積したものを無性にアウトプットしたくなってしまって、結果、番組の企画を作り、プレゼンして通してしまったわけです(笑)。
──腰掛けのつもりだったのに(笑)。
中曽根:そう、やらなきゃいいのに、ついつい「これをやりたいです」と言っちゃって(笑)。そのときに出会ったのがアンドレア・ポンピリオ氏で、彼はイタリアと日本のハーフで英語もイタリア語もできるし「今の日本に足りないもの」みたいな話も合ったので「一緒に番組をやろう」と。これまたラジオ経験ゼロの人間を大抜擢した企画でした(笑)。
──(笑)。
中曽根:結局、その企画はJ-WAVE毎週土曜日の『MODAISTA』という3時間番組になるんですが、『MODAISTA』は「東京の人たちに世界の遊び心を注入する」みたいなコンセプトの番組で、海外のいろいろな情報を単に届けるだけじゃなくて、2か月に1度は世界のどこかへ行って、現地から放送するということをしていました。ラジオの可能性として、テレビと違いコストをかけずフットワークよく「世界のどこからでも放送できるんだ!」というのを見せつけたかったんですよね。
──中曽根さんの旅の経験が生きたんじゃないですか?
中曽根:そうですね。自分も帰ってきたばかりでしたしね。それでアジア各国からの放送もやりましたし、バルセロナで開催されたソナーというフェスティバル会場からの放送もしました。そんなにかからないとはいえ予算の問題などもあったので、僕は企画書を持って航空会社や観光局などへ行ってタイアップを見つけてきました。それでモントルー・ジャズフェスからとか、パリ、シンガポール、ラスベガス、ニューヨーク、オーストラリアと世界中から放送しました。
──それは中継でやるんですか?
中曽根:生放送です。時差も計算して。でも、ちょっとした機材が1個あればやれちゃうんです。テレビはすごく大がかりなところが、ラジオは全然簡単で、今だったらもっと簡単ですし、そういう番組がたくさんあってもおかしくないと思うんですが、みんな面倒臭がるのと、そもそもやる人がいないんじゃないですかね。
──やる人というか中曽根さんみたいにやれる人がいないんでしょうね。
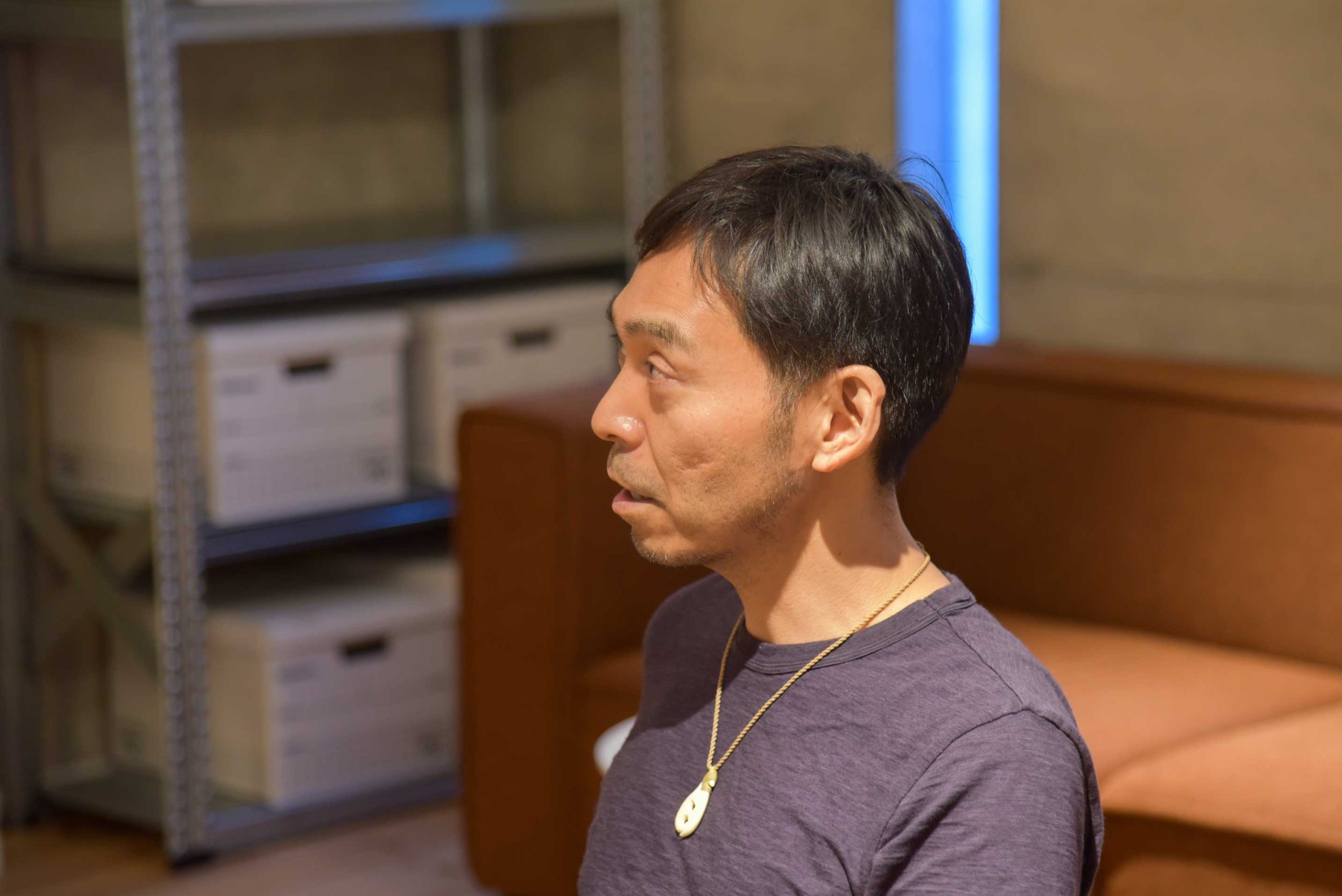
中曽根:あと、その頃出会った音楽プロデューサー、ラジオDJのジャイルス・ピーターソンの存在も大きかったです。彼はアシッド・ジャズムーブメントの火付け役みたいな人ですが、ルーツは完全にラジオで、自分で海賊ラジオをやり始めたのが原点なんです。その彼のパワーを日本でも伝えたいと思って、これも結果J-WAVEになったんですが、ジャイルスがUKでライフワークでずっとやっている『WORLDWIDE』という音楽番組の東京向けオリジナル番組『WORLDWIDE 15』を制作してもらいました。
彼との関係は今でも続いていて、ジャイルスが6年前に「WORLDWIDE FM」という自分のラジオ局を立ち上げたんですが、その際に「立ち上げを手伝ってほしい」と相談されて「なにすればいい?」と言ったら「スタッフが1人欲しい」みたいな話になったんですよ(笑)。それで、もともとニューヨークにいて、その後シャ・ラ・ラの社員になり、一緒にジャイルスの番組もやっていたスタッフがロンドンにいくことになり、それで現地にシャ・ラ・ラのロンドンオフィスができました。
──シャ・ラ・ラ・カンパニーもずいぶん国際的になったんですね。
中曽根:ジャイルス・ピーターソンとの出会いや、アンドレア・ポンピリオと一緒に番組をやったことで一気に海外志向の社風になったと思います。そのときは日本のメディア、特にFM局はまだまだJ-POP志向が強かったのと、海外というとどちらかというとアメリカ寄りだったんですよね。だから、ジャイルスの存在によって、ヨーロッパへ目を向かせられるチャンスだなと思いましたし、アメリカ偏重型になるのではなく、それとはちょっと違う風を吹かせることができるかなと思っていました。
──確かにどうしてもアメリカが中心になってしまいますよね。
中曽根:インターFMもすごくアメリカンな感じでしたし、J-WAVEもジョン・カビラさんにしてもクリス・ペプラーさんが中心だったので、気づいたらみんなアメリカなんですよ。ジャズも結局アメリカのジャズが大半を占めていました。もちろん素晴らしい音楽はアジアやアフリカ、中南米とか色々あるんですが、まずはヨーロッパから新しい風を吹かそうと思って、すごく意図的にヨーロッパ寄りの番組を作っていました。
──中曽根さんがシャ・ラ・ラに完全に復帰したタイミングというのはいつになるんですか?
中曽根:自分で企画提案した番組をやっている時点で、もう抜けられないというか、抜ける感じもないですよね。
──ちなみに当時の名刺の肩書きはどうだったんですか?
中曽根:そのときは「クロスオーバープロデューサー」みたいな(笑)、適当な名前をつけていましたね。そうこうしているうちに、佐藤社長が急にというか計画的に「引退したい」という話になって、社内での先輩は何人かいたんですけど、自分の目の前に彼からのバトンが置かれ、そのバトンを持っちゃったみたいな感じですね。どこか佐藤社長にもラジオ業界にも、充電した自分で恩返ししたいとも感じてましたし。
──大抜擢ですよね。
中曽根:そうですよね。まだ35、6でしたから。
──そのときはどう感じられたんですか?
中曽根:前も自分の会社で社長をやっていましたし、「まあ、なるようになるさ」という感じですよね。前にやっていた会社は完全に自分で資金も入れてやっていたのに対し、今回は雇われ社長だと思うと少し気が楽でした。
──なんかまた旅に出たくなっちゃうんじゃないですか?
中曽根:なっちゃっても雇われ社長なので出ていいかなって(笑)。
──(笑)。
中曽根:確かそのぐらいのタイミングでリスペクトレコードの高橋さんから「『MODAISTA』という番組は世界のいろいろな音を取り上げているけど、こんな面白いものもあるよ」と沖縄の音楽を紹介してもらったんですよね。もちろんそれまでも沖縄の音楽には触れていましたし、好きか嫌いかで言うと嫌いじゃないけど、それよりも欧米の音楽のほうを優先して聴いちゃっていたので、深入りするきっかけがなかったんですよね。
ラジオ番組作りの集大成『ネイティブミュージックジャーニー』とポッドキャスト
──中曽根さんが考える沖縄の魅力はどういうところですか?
中曽根:僕は音楽が入り口ですが、歴史を知れば知るほど、あんな小さな島なのに底力がすごいなと思うんですよね。みんな陽気で「なんくるない」みたいな印象なんですが、その根底には「絶対負けない」みたいな気概があるんですよね。琉球の時代から中国にいい顔しなきゃいけない、でも日本にもいい顔しなきゃいけないみたいなところで生き、結局、戦争になって、あんな焼き野原になった中からでも立ち上がってね。あれを経験している今の沖縄のおじい、おばあたちは本当にすごいと思います。
沖縄は小さい島ですが、楽しく生きるためにいろいろなものを自分事として取り入れて、民謡はもちろんだけど、ジャズ、ロック、あとラテン系の音楽をやっている人たちもいれば。踊りだって琉球舞踊もあればサンバやフラをやっている人もいる。とっても多様で、しっかり地に足ついた力強さがある。
──なるほど・・・。
中曽根:そして、2018年頃ぐらいから自分の中で「ラジオ番組作りの集大成フェーズに入ったな」と思っていたら出てきたのがポッドキャストで「またなにか面白いことが始まっちゃうのかな」と思ったんですよね。そこで、放送としての集大成と、ポッドキャストを入り口とした新たな音声コンテンツに取り組むようになったんです。
放送番組の集大成に関しては、商業的な音楽でなく人々の生活と結びついた音楽、いわゆるワールドミュージック、ルーツミュージックをテーマにした『ネイティブミュージックジャーニー』という3時間の特別番組を春夏秋冬と1年に4回を、2年にわたって制作しました。これはテレビの海外ロケ番組企画みたいなもので、以前から興味を持っていた台湾の原住民たちの音楽や、インドネシア・バリ島の音楽、ハワイ、タヒチ、北欧などの音楽などの現地取材しました。
──すごくディープな番組ですね。

中曽根:集大成ですから、これぐらいやっておこうと(笑)。ヨーロッパも旧ソ連の先住民の人たちの音楽や、ずっと前から興味があったエストニアへ長期ロケに行って、森の中で紡がれる、森の妖精のような音楽と言いますか、ハープと日本の琵琶を足したような感じの『カンネル』という楽器の演奏などを取材しました。エストニアって実は歌で独立を勝ち取った歴史のある国なんですよ。合唱に次ぐ合唱で「そこまで歌うんだったらいいよ」と独立を勝ち取った歴史があって、5年に1回、ソングフェスティバル的な大合唱大会が開催されるんですが、そのときはエストニアじゅうから民族衣装を着た人たちがタリンという首都にある合唱用のスタジアムに集結して、そこで30万人が大合唱をするんですよ。
──すごいですね! それは全く知りませんでした。
中曽根:エストニアはそういうことも含めて興味がある場所だったので長期ロケをしておこうと。最終的にその番組でギャラクシー賞の優秀賞をもらいました。まあJ-WAVEが応募してくれてそうなったんですけど(笑)。結局そういうロケをコロナの直前まで8か所行ったんですが、コロナぎりぎりの8回目のロケがタイで、帰国する途中に「急に便が欠航なんだけど、一体どうなっているんだ?」と(笑)。
──本当にギリギリだったんですね(笑)。そして、もう一方がポッドキャストですか。
中曽根:そうですね。結局ポッドキャストはシャ・ラ・ラのもうひとつの事業として形になりつつあります。ポッドキャストがすごいのは、ひとつ番組を作れば、様々なプラットフォームで配信することが可能なところで、普通ラジオだったらそんなことあり得ないじゃないですか?ニッポン放送とTBSとJ-WAVEとTOKYO FMで同じ番組を聴けるわけにはいかないですから。
──ポッドキャストはそれができると。
中曽根:これはやっぱりいいですよね。自分たちみたいなプロダクションカンパニーって音声コンテンツはどんどん作れるじゃないですか? ですから、これからは各局からのオーダーを受けつつ、例えば、Spotifyオリジナルのポッドキャストとか、企業やブランドのオリジナル・ポッドキャストを作るという仕事も同時にやれればと思っています。
──ポッドキャストに関連して、シャ・ラ・ラ・カンパニーがやっているNR9とは一体どういうサイトなんですか?
中曽根:NR9はまだ実験段階なのですが、一言で説明すると独自のセンスでセレクトしたポッドキャストのキュレーションサイトですね。ポッドキャストの課題って「どれを聴いていいのかわからない」ことだと思っていて、NR9ではタワーレコードの店員がおすすめのCDにポップを書くように、ポッドキャストも熱いレビューを書いてリコメンドすることをやってみたら面白いかもと始めたサイトです。その昔ファッション業界でインディペンデントで質の高いブランドががたくさん生まれ、それをセレクトするビームスやユナイテッド・アローズが生まれたみたいなかんじです。
──ちなみにポッドキャストの収益のあげ方ってどういう方法になるんですか?
中曽根:収益を狙うのであればスポンサーを付けるか、あとは有料化、サブスクするみたいなかんじですかね。アメリカではすでにポッドキャストのサブスク化が進んでいるんですが、日本では現状なかなか難しいかなと思っています。
──その加減が難しいところですよね。
中曽根:NR9は社内の若手社員たちのチャレンジの場としてあくまでもキュレーションにこだわり続けたいですが、音声コンテンツとしての収益化はもっと別の形でやろうと思っています。まだ模索段階ですが、音声コンテンツをもっとマス向けではなくインナー向けのものしたいと思っています。放送局の番組制作とは全くの別物として、来年までには新しい概念の音声コンテンツのシーンを確立させようといろいろやっています。
音声コンテンツが海外へ出ていく可能性を探りたい
──現在、中曽根さんはシャ・ラ・ラ・カンパニー代表取締役会長という立場ですが、実務もまだされているんですよね?
中曽根:はい、やっています。会社の枠をこえて業界のために役立つ会長あらため、「界長」が目標です。今後はラジオという船に乗っている、同じような制作会社の人たちと、たくさんコミュニケーションをとって、「まだまだラジオ業界って夢があるよ」と言えるぐらいにしていきたいんですよね。放送局の人たちとも「一緒になって乗り越えていきましょう」と言い合いたいですしね。
──中曽根さんの集大成モードの先にはラジオ業界全体の改革があると。

中曽根:そんな大それたことになるのか、もっと違ったことになるのかわからないですが、手軽に音声コンテンツができる時代になっていけばいくほど、ラジオの未来への危機感があるんです。あとポッドキャストのように「音声コンテンツってこんな簡単に作れちゃうの?」と思われるのも、風通しが良くなっていいなと思う反面、プロとして「いやいや、そんなに簡単じゃないよ」とどこか思っているんです。
個人的にはラジオが今まで培ってきた、DJがいて、ターンテーブルやCDプレイヤーあって、ディレクターがキューを出してみたいな、そういうラジオの様式美みたいなものも、残さないといけないというより、残したいんですよね。
──最後になりますが、ラジオの仕事に興味がある若い人たちにメッセージをいただけますか?
中曽根:個人的には、数年前までラジオ業界って「沈みゆく船かもしれない」と思っていたんですよ。ですから「お金でなく好きなことがが仕事になればいいです」、という人じゃないとラジオ業界に誘えないという想いがあったんです。どんなに音楽が好きでも、ラジオの音楽番組ってすごく少なくなっていますし、ラジオでの芸人の話が大好きだという人でも、それだったらラジオじゃなくてYouTubeでいいんじゃない? という時代になるかもしれませんから。
──(笑)。
中曽根:ただ、世界的にポッドキャストをはじめ、音声コンテンツの可能性を見つめ直そうみたいな空気になっているのは確かですし、これを面白がれる人たちなら、チャレンジする価値はあると思うんです。ラジオもポッドキャストも互いに相乗効果をもったかんじで。あとアニメや漫画が海外に出て外貨を稼ぐのと同じように、音声コンテンツも海外へ出ていく可能性を探りたいなと思っています。今はいつでも外へ飛び出せる環境ですし、その扉を開いていけるような人材が集まれば、これから面白くなる業界なのではと思います。ラジオと音声コンテンツの無限の可能性を信じて、是非一緒にチャレンジしましょう。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載