Spotifyのダニエル・エクCEO「AIは脅威でなく、音楽の創造性を促す」スーパーファン戦略や値上げにも言及

AIは将来より多くの人々に音楽制作を促すもので、業界にとって脅威ではないーー。ダニエル・エクCEOらSpotify幹部が5月の最終週、ストックホルム本社で開いた記者向けのオープンハウスイベントでAIなどについて語った。
エク氏はAIについて「われわれはより多くの人間がアーティストとして成功することを望んでいるが、AIが存在する未来におけるクリエイティビティー、音楽とは何だろうか?」と疑問を提起。音楽とテクノロジーの歴史に触れながら、「今、われわれが利用できるツールは驚くべきもので、AIには非常に恐ろしい応用の可能性があるが、私にとってもっと興味深いのは、クリエイティブな人々が指先で利用できるようになる創造性の量がとてつもないものになること」とし、音楽業界におけるAIの発展は「革命というより、むしろ進化」だと述べた。
同社によると、現時点でSpotifyにおける「完全にAIが生成した楽曲」の消費は非常に少なく、ロイヤリティーの希釈はないという。
また、生成AIにより、リスナーがアプリを単にタップするのではなく、Spotifyと会話(プロンプト入力)するようになることで、リスナーをより深く理解できると期待している。
このほか、スーパーファンについては、既存の「ファン・ファースト」イニシアチブ(熱心なファンを対象とした、チケットやグッズ購入の招待Eメール)のように、アーティストや消費者に素晴らしい体験を提供するため、さらに何ができるか考えていると説明。さらに、値上げが顧客を遠ざけるリスクを強く認識していることも明かした。
(文:坂本 泉)
榎本編集長
「Spotify創業者エク氏が「AIには非常に恐ろしい応用の可能性があるが」と条件付きで「AIは脅威でなく、音楽の創造性を促す」と見解。脅威という麺では、SpotifyはAIによるストリーミング詐欺を再生の1%未満に抑えているのでコントロールできている。次に創造性だが、新潮で音楽とAIについて連載した経験から言うと、簡単なプロンプトで演奏力や音楽理論を知らなくても楽曲が生成できること自体は感動を与えたが、生成AIブームからこれだけ経ってもヒット曲が出ないのは、音楽というのはどこまで商業化してもアートであり、数千人、数万人の心を動かす感動を作り出せないと売り物にはならない。それには意味を理解する汎用人工知能の登場が不可欠だが、AI研究者の8割近くが現時点のAIにいくら計算能力とデータを与えてもそれは不可能と認識している。生成AIの技術的基礎となるニューラルネットワークは静止画を認識する神経作用をモデルとしており、時間の芸術である音楽と根本的に合ってないところがある。ただ連載でも触れたが、グーグルが方向転換してミュージシャンの創作活動をサポートするAIの開発に向かったように、生成AIを精緻に駆使して新しい形式を生み出す次世代のアーティストはいずれ増えるだろう。ディープラーニングを超える技術革新が起きるまでは新しい楽器、新しいメディアとしてのAIが追求されると私は思っており、それはある意味、サンプラーやDTMあるいはストリーミングで大きな技術革新が止まってしまった楽器やメディアを進化させ、ロックやヒップホップ、EDMに続く新しいメガトレンドを生み出す可能性はある」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
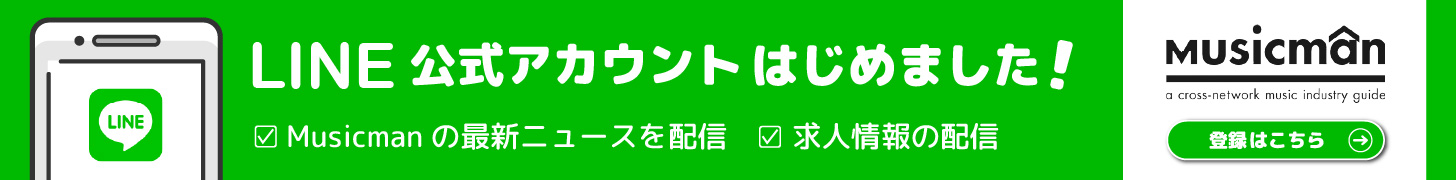
広告・取材掲載