【全文掲載】日本の音楽サブスクはあとどれくらい伸びる?【榎本編集長のMusicman大学#4】
MC Tama: 榎本先生、今回はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか?
榎本: いつもバズったニュースから取り上げてるんですが、今日の話題は「Spotify欧州有料会員1億人突破」っていうこのニュースがなぜかバズりまして、これにどんな意味があるのかということを説明していこうかなと思います。
MC Tama: よろしくお願いします。
1億人は多いのか少ないのか
榎本: まず1億人って多いのか少ないのか。この数字って、「欧州」って書いたんですけど、EUとイギリスを足した有料会員が1億人突破したってことなんですね。EUとイギリスの生産年齢人口っていうのがあるんですけど、16歳から64歳までをそう呼ぶんですが、それがね、だいたい3億人なんですよ。3億人ってことは、有料会員Spotifyの1億人だってことだから、3人に1人がSpotifyの有料会員なんですね。これはTamaさん、いかがですか?
MC Tama: 多く感じます。まだまだ伸びしろがあると思いますよ、1億人だと。もっといくと2人に1人とか。これSpotifyだけでしょ?Apple Musicもあるじゃないですか。
榎本: 向こうだったらDeezer、フランスの音楽サブスクもそこそこ人気があって、そういうのを合わせると、多分ね、生産年齢人口の2人に1人が音楽サブスクの有料会員になっているということなんですね。これが多いか少ないかなんですけど、これは多分ほぼピークに来たかなと思います。前回もちょっとお話ししたんですけど、先進国で音楽サブスクが伸び悩んでいると。まあ、2人に1人入ったらもうほぼ限界かなっていうね。
そもそも音楽って今の時代って無料でも聴けるじゃないですか。広告付きでね、例えばYouTubeとか、あと最近だったらTikTokとかで。Spotifyも無料プランもあるし、無料でいいやっていう人もそれなりにいるんで、2人に1人は十分上出来かなと思ってます。
日本の状況は?
MC Tama: ちなみに日本ではどうなんでしょうか?
榎本: これ大事なんですけど、だいたい僕の計算だと2000万人くらいですね(※動画の数字1500万人を最新の分析の数字に変えました)。だいたい日本の生産年齢人口というのが7450万人くらいなんですね。トータルの人口は1億2000万ですけど、7450万人が生産年齢人口。これの、だいたいだから、そうですね4分の1ちょいぐらい今入ってる。4人に1人ぐらい。ヨーロッパは2人に1人。
MC Tama: 日本はまだまだ伸びるってことですね。
榎本: 日本は音楽サブスクはもっとどんどん伸びる。つまり、2人に1人、生産年齢の2人に1人って約3700万人。今2000万人ってことは、今の2倍弱は増やせるんじゃないの?っていう感じになるんですよ。
日本の音楽配信売上の現状
MC Tama: 榎本先生、日本ってCDがすごい強い国じゃないですか。サブスクの売り上げって今いくらぐらいあるんですか?
榎本: サブスクっていうか、音楽配信の売り上げっていうのがだいたい4割弱ぐらいです。日本の音楽ソフト売り上げ、つまりライブの売り上げとか別として、CDとか音楽配信の売り上げっていうのを合わせると、だいたい3000億円強、正確には去年3285億円だったんですけど、その4割ぐらいが音楽配信になっていて、残り6割がCDとかDVD・ブルーレイなどなんですが、今後ヨーロッパのあるいはアメリカの状況を見ると、8割から9割は音楽配信になっています。
やっぱりなっていくんですよね。なぜかっていうと理由は簡単で、CDプレイヤーって、例えばTamaさん持ってらっしゃいますか?
MC Tama: 今まだね、捨ててないです。あります。
榎本: CDはありますか?
MC Tama: ちなみに、だいぶ整理しました。今サブスク、やっぱり私もApple Music使ってるんですけど、携帯とかパソコンとかで全部検索すると、すぐ好きな曲を聴けるじゃないですか。CDってどこに行った?って。もう大量に持ってたので、もう本当に「ここだっけ、ここだっけ」って探しながらで、やっと聴けるっていう感じだったんですけど、一回携帯とかパソコンでApple Musicとかで検索して聴けるようになっちゃうと、もうその楽さが本当に日常化してしまって、CDを聴くっていう流れにならないんですよね。
榎本: その気持ちはよくわかりますね。Apple Music、音もいいし、曲もずいぶん揃ってて。
MC Tama: そうですね。一時はなんか「CDにあれがない、これがない」んだっていうものあったんですけど、最近結構レアなものも入ってきましたよね。
榎本: そうですね、確かに。そうなんだよな。ただ、すごくサブスクで寂しいのは、ジャケットが目の前にないのが寂しいんですよ。解説が読めないとか。
MC Tama: そう、解説読めないのはね。解説読むの結構楽しかったですね。
榎本: そうそう。あれ勉強になりますからね。
MC Tama: そうなんです。「こういうルーツ持ってんだ」。
榎本: サブスク、我々はもうCDの時代からやってるじゃないですか、同世代なんですけど。あの時に楽しかったことって、ジャケットで買って飾っておくとか、今おっしゃったようにライナーノーツ読んで勉強して、「こういう背景があるんだ」って。あれがないのは、音楽体験がちょっと、ね、ちょっと残念かなって。
ただApple Musicって、最近Apple Musicのクラシック専用のアプリできたんですけど、それはねもうばっちりライナーノーツが付いてますね。
MC Tama: あ、そうなんだ。それは知らなかったです。
榎本: 多分、そのうち普通のやつにもライナーノーツが付くんじゃないかなと思ってますけどね。
世代による音楽の聴き方の変化
MC Tama: うん、うん、うん。お子さんCDプレイヤー持ってます?
榎本: 持ってないです。
MC Tama: 持ってないでしょ?
榎本: はい。ちなみに俺もCD再生できるのって、パソコンしかなくて、子供いるんですけど、CDプレイヤー持ってないんですよ。でやっぱり、もう今の10代の子たちってデジタルネイティブ、スマホネイティブ世代って呼ばれてて、もうコロナのあたりからスマホ、小学生で持てるようになってたじゃないですか。それで音楽聴けるようになったんで、CDプレイヤーもそもそも持ってない。
MC Tama: そうなんですよね。携帯一つあれば、もう聴きたい曲がほとんど聴けるようになってる時代ですからね。
榎本: そうそうそう。だからその10代の子が10年後20代になってる。その子たちがまた30代になってる。日本の音楽産業って主なお客さん、やっぱり15歳ぐらいから34歳ぐらいまで。音楽離れって2回起こるんですよ。まず社会人になった時、忙しくなって。あと、これはちょっとTamaさんも俺も音楽業界だったんで、ちょっと別の例になっちゃうんですけど、普通の方、音楽の話って大学生の頃はしてますよね。別に音楽、特に音楽マニアってわけじゃなくても、友達と音楽の話してるじゃないですか。会社に入ったら同僚とか上司とかとあんまりそういう話ってしないんですよね。そうすると音楽離れが始まっちゃうんですよ、忙しくなるっていうのもあるし。
もう一個は34歳、何が起こっているかというと、お子さんができたり、あるいは仕事でちょっと立場が上になったりして、さらに忙しくなっちゃう。そうするとまた音楽離れがガッと進むってなってて。つまり、30歳までに今の10代の子たちが10年後、15年後になっちゃってるんで、そうするとCDの時代って、どんなにCDが強いって言ってても、やっぱ望みは薄いですね。
日本の音楽サブスク市場の今後
榎本: で、今だいたい最新のデータ、レコ協のデータから見ると、今年の音楽サブスクの売り上げって多分ね、1000億いくかいかないかぐらいになります。でそれの2倍強なんで2000億ちょい、まあよくて2500億で、まあCDがどれくらい残るかっていうのを考えると、やっぱり3000億円ちょい超えるぐらいで止まっちゃう。CDはどんどんなくなっていくし、音楽聴く年齢っていうのはこの国の場合、少子高齢化が進んでるんで、どんどん減っていくんですよ、メインターゲットが。
そうするとやっぱり、サブスクでさっきの15歳から64歳まで広く有料会員になっていただかないといけないっていうのは当然あります。だけど、それだけだと足りない。
MC Tama: 今日本は2000万人の人がサブスクを利用してるじゃないですか。これからサブスク人口3700万人になる日は来るんでしょうか?
榎本: はい、えーっと、そうやって成長率を見てればだいたいわかるんですね。でこの調子でいくと、結構かかっちゃう。なぜかっていうとですね、日本の音楽サブスクの成長率って年々どんどん落ちてるんですよ。2022年頃、今から3年前、日本の音楽サブスクの売り上げって19%上がったんですね、2割ぐらい。次の2023年、13%。次の2024年、9%。どんどん下がってる。今年の1月から3月までのデータだと5%。どんどん下がってる。5%で2倍以上にするとしても、ざっくり言って16〜17年かかる。さらに実際にはどんどん下がってきかねない、20年以上このままだとかかってしまう。
ただ、さっきも話題に出たCDプレイヤーっていうのがどんどんなくなると思って、それ考えた時、そのどんどんどんどん落ちていくって言っても、どっかで下げ止まるかなと思ってます。と言ってもちょっと時間がかかるし、世界の音楽売り上げってサブスクの登場したことでV字回復したっていうのは前解説したじゃないですか。そういう感じにはやっぱなんないかな。つまり、まあ下げ止まったけど、そのまんまこう横ばいになっていっちゃうっていうことになるかなと思います。
サブスク以外の稼ぎ方
MC Tama: サブスクだけじゃダメだったら、どんな稼ぎ方があるんですか?
榎本: ということを音楽産業としては考えなくちゃいけなくて、まず一つが前回説明した海外進出ですね。日本の音楽っていうのも海外に輸出していく。日本の音楽マーケットって世界でずっと2位をキープしてたんで、今でも2位なんですけど、あまりにも素晴らしいマーケットだったんで、どうしても日本国内ばっかり相手してたんですけど、このままじゃいかんっていうのがもうピンチを感じてるで、かつチャンスも感じてるっていうのを前お伝えしたんですけど、今年グラミー賞を主催するレコーディングアカデミー・アメリカの、今年今までのK-POPみたいにJ-POPみたいな話が出てきてて、前回の動画を見てもらいたいんですけど、実際にいろんな事例も出てきてる。それが一つ目。
じゃあ国内どうするの?っていう話になるじゃないですか。海外は海外でもちろん出てくるけど、国内はどうするの?と。これは他の先進国も一緒なんですよ。サブスクが上限に、ライブの売り上げも本当にピークに来ちゃってて、今までサブスクとライブで伸ばしてたけど、これ以上伸ばすんだと何かやらないとねっていう話になってて、その中のいくつかあるのが「スーパーファン」っていう言葉があります。
次回予告
MC Tama: では榎本先生、質問なんですけど、スーパーファンって今ワードが出てきたんですけど、これについてもっと詳しく聞きたいんですけど。
榎本: これ超重要キーワードなんですが、日本だと課題もあるし、ちょっと時間がかかるんで、次回説明させていただければと思います。
MC Tama: ありがとうございます。よろしくお願いします。
プロフィール
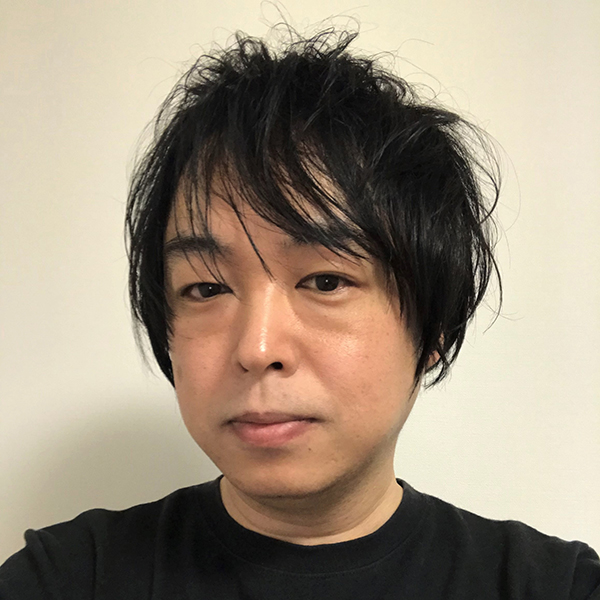
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。Musicman編集長・作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。著書に「音楽が未来を連れてくる」「THE NEXT BIG THING スティーブ・ジョブズと日本の環太平洋創作戦記」(DU BOOKS)。『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載。
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
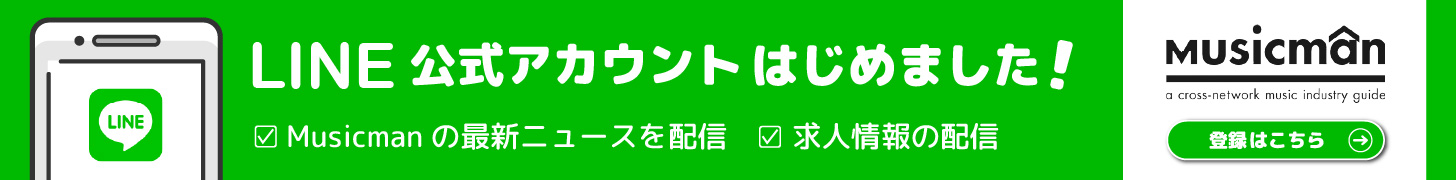
広告・取材掲載