
旅をするとは、その地で暮らす人たちが一瞥もくれない存在に対して、新鮮に驚くことなんだと思う。見慣れない標識を、スーパーを、あるいは電車を、思わず写真に収めたくなるほど、目に映るどれもが輝いて見えることなのだろう。であるならば、その街で暮らすとは、居を構えた時にはピカピカに思えた街並みが気にも留めない背景に変わっていくことなのかもしれない。
フロム札幌の4人組・goethe(ゲーテ)が10月10日(金)に産み落としたEP『Town e.p』には、そんな馴染み切った風景の美しさを呼び覚ます全5曲が収められている。お互いを分かり合うために話し合いを重ね、メキメキと成長を遂げてきた彼ら。各地を巡る中での出会いや気づき、街と人の繋がりを紐解く中で生を受けたこの作品は、間違いなくあなたの住む街とも重なるはずだ。
■「平熱に見えるけれど、中には熱い思いがあり、説得力もある」(加藤)
――goetheは、樋口さんの温かな歌声や柔らかいアンサンブルをはじめ、心地良い平熱感を持っているというか、ニュートラルであることを受け止めてくれるバンドだと感じていて。リリックを拝見しても、決して強引に引っ張り上げるのではなく、解けた靴紐を結び直してあげるような言葉が並んでいると思うんです。皆さんはgoetheの音楽をどのように受け止めていらっしゃいますか。
樋口太一(Vo,Gt):おっしゃっていただいた通り、goetheは聴いてくれている人の肩を支えてあげるというか、寄り添うような視線が多いバンドだと思っていますね。あと、特に最近はしっかりとポップスをやりたいという思いで曲を作っていて。これまでは横で支えてあげるような姿勢を大事にしてきたんですが、「Q」をはじめ、高いところから手を差し伸べるというか、引っ張り上げるスタイルに変わりつつある。とにかく聴いてくれている人のことを考えながら楽曲を作っていけたらなと。
――スタイルの変化は最新作『Town e.p』からも伺えるところですが、そもそも寄り添う音楽、ふとした時に傍にある音楽を鳴らしたいと思うようになったキッカケは何だったのでしょう。
樋口:そういう音楽をやりたいと思う機会があったというより、自分の性格的な側面が大きくて。というのも、自分から何かを発信したり、引っ張っていくようなタイプじゃなかったから。人の話を聞くのも好きなので、自分の中から自然に出てきたものがgoetheのイメージになっていったんですよ。
――リーダー気質だったわけではなく、フォロワー体質だったことが反映されていると。ポップスをやりたいとも語っていただきましたけれど、その思いはなぜ生まれたものなんですか。
樋口:純粋にポップスを聴いて育ってきたのもありますし、初めて好きになったバンドがMr.Childrenだったんですね。そこから影響を受けて自分も音楽をやってみたいと思うようになったんです。もちろん、いわゆるアンダーグラウンドの音楽も好きなんですけど、やっぱりポップスにルーツがある分、自然と出てくる音楽にはなっています。

樋口太一(Vo,Gt)
――なるほど。では樋口さん以外のみなさんはgoetheをどのようなバンドだと感じていますか?
永江碧斗(Key):僕はgoetheのことをソウルフルなバンドだと思っていて。僕自身プレイしていても心の奥底が沸々と燃え上がるような気持ちになりますし、きっとお客さんもそういう気持ちになっているはず。心の奥にあるものに訴えかけることができるんじゃないかなと。
加藤拓人(Ba):先ほど、平熱とおっしゃっていただいたと思うんですけど、僕もgoetheは平熱という熱量を正しく伝えられるバンドなんじゃないかと感じていたんです。でも、バンドを進めていく中で、一人ひとりに強いこだわりや凄い熱量があることが分かって。平熱に見えるけれど、中には熱い思いがあり、説得力もある。そういうバンドにどんどん変わってきていると思いますね。
――奥底に秘められた熱量が可視化されるフェーズに突入した。
加藤:そうですね。もともとメンバー4人とも感情が表に出るタイプじゃないですし、友達みたいな状態から始めたバンドではなかったので、ある種の距離があったというか。だけど、腹を割って話してみたら、みんなも腹を割って話してくれて。お互いを分かり合える機会がどんどん増えてきたんですよ。というのも音楽をきちんとやっていく以上、どういうバンドになっていきたいのかを話す必要があったんですよね。1回だけじゃなくて、何回も腹を割って話さないといけなかった。そういう会話を積み重ねたことで、それぞれの思っていることを理解できるようになってきたんです。明確なキッカケがあったわけじゃないんですけど、ちょっとずつ変化し続けているのかなって。
永江:確かに、メンバーで会話を重ねるようになってから、演奏の中でお互いを意識する瞬間が増えた気がしますね。きっともともと各自が熱い思いを抱いていたんですけど、その方向性はバラバラだった。でも、話し合いを重ねたことでその方向がまとまって、4人の音がバチッと合わさった時に熱量を感じてもらえると思います。
相蘇勇作(Dr):3人はgoetheが変わりつつあると話してくれましたけど、逆に太一(樋口)の声を活かす楽曲作りはこのバンドを始めてから変わってないと思っていて。全員が“太一の声が好きだ”っていう思いで集まっているからこそ、太一の声を活かせる楽曲や彼のイメージを落とし込んだ歌を作っている。そこは一貫し続けているポイントだと感じていますね。

永江碧斗(Key)
――結成当初から、樋口さんの歌声を引き立てる楽曲作りが念頭にあったと。
加藤:というよりも、太一と色んな形で出会う中で、それぞれが彼の歌声に惹かれていたんだと思いますね。僕は高校の頃から太一と一緒なんですが、太一の歌声を聴いて“一緒にバンドをやりたい”と強く感じましたし、僕と太一でやっていたバンドを見てくれた碧斗(永江)も同じ感情を抱いてくれたんじゃないかと思いますし。
――過去のインタビューにて、結成当初はyonawoやTENDREをベンチマークにしていたという旨も拝読したんですが、そうした音楽性をモデルにしていた背景は樋口さんの歌声を引き立てるため?
永江:確かに、言っていただいたようなジャンルと太一の歌声が合うだろうという確信はありました。
樋口:そうだったんだ……。僕は話すことが得意じゃないんですけど、歌だけはストレスフリーというか、自然にできることで。だから、自分の歌を尊重してくれるメンバーがいて有難いですね。
――樋口さんはお話が得意ではないと感じていらっしゃるとのことですが、歌であれば自然に思いを乗せられるのはなぜなのでしょう。
樋口:喋りだと人並み以下からスタートしなきゃならない一方で、歌であればみんなと同じステージに立てるというか。というのも、中学校の合唱コンクールで自然と歌えた経験が大きかったんですよ。最初は歌うことも恥ずかしかったんですけど、先輩の合唱を聴いていたら“人の声って凄いな”と思った。そこから、歌うことも恥ずかしくなくなって、歌うという行為が自然とできるようになったんです。
■「聴き終えた時、スッキリとした気持ちになれるEPになった」(永江)
――10月10日に前作『内なる惑星』以来およそ8カ月ぶりとなるEP『Town e.p』がリリースされました。秋空に吸い込まれていくようなコーラスワークとホーンサウンドが特徴的な「Town」や、ノスタルジックな手触りの「夢から覚めても」をはじめ、先ほどからお話にも出ていた変化や広がりといったワードが浮かんでくる1枚だと感じています。また、<暖かい光 ひかり 何度でも今救ってあげるよ>と歌う「Q」を筆頭に、これまで以上に強く手を取ろうとする力強さも滲む作品だと受け止めているのですが、本作を振り返ってどのようなEPになったと感じていらっしゃいますか。
永江:聴き終えた時、スッキリとした気持ちになれるEPになった手応えがありますね。「Town」では<澄んだ空気が目に染みて あなたのいない街で>と歌っていますし、秋らしいサウンドを使っていますけれど、どこか寂しくて、それでもスッとするようなポイントが散りばめられている。どの曲を聴いても楽しんでもらえる、バラエティーに富んだ作品になりました。
加藤:歌詞の内容としても、音楽的にも幅広い作品になったと感じていますし、goetheにとって財産となる一枚だと思っています。あとは『Town e.p』という名前の通り、この5曲を通じて、自分が住んでいるいつもの街を再発見できる気がしていて。何となくその街で生きていると同じ景色を毎日見る分、気にも留めないことも多いじゃないですか。でも、このEPの中で描かれている色んな情景を、それぞれの頭の中で浮かべたタウンに当てはめたり、その街で見るものや食べるもの、触れるものと重ねてくれたら、気づきがあると思う。日常に寄り添ってくれる聴きやすさも、新しい発見を与えてくれる新鮮さも、どちらも兼ね備えた作品になりましたね。
相蘇:2人が言ってくれたように、ストーリーも楽曲の幅もそれぞれ違う切り取り方ができたんじゃないかなと。サウンド的に挑戦した楽曲もありますし、「moon」や「hibi」のようにこれまでのgoetheらしい雰囲気を纏っている歌もある。今までのgoetheをまとめ、アップデートできたEPだと感じています。

加藤拓人(Ba)
――おっしゃっていただいたように、今作ではボサノバ調のギターや豊かなコーラスを取り入れたりと、サウンド面が大きく拡張されているじゃないですか。この一枚でそうした新たな音像に挑戦した理由は何だったのでしょう。先ほど数々の話し合いを経て、ポップスをさらに追及するようになったともお話いただきましたけど。
樋口:自分の中ではポップスって、歌のメロディーを心地よく、楽しく、キャッチ―に聴かせるものだと思っているんですね。で、そういう心地良さを追求することを考えると、もちろんシンプルにしていくやり方もあるんですが、色んな要素を足したり、強弱を付けたくなったりするんです。そうやって楽曲に違いを出す方法を考えた結果、サウンド的にもどんどんクリアになってきていたので、様々な要素を取り入れることにしました。
――サウンド面がクリアになってきたというのは、音数を増やしたとしても、メロディーの引き立つバランスを見つけられたということ?
樋口:クリアっていうのは音質のことで、「この曲はこういう音像にしたい」っていうイメージが明確に見えるようになってきたんです。例えば、「夢から覚めても」はもともと好きだったいなたい雰囲気を出そうとしましたし、「Q」はポップスのステージで戦うためにトレンドでもある打ち込みの要素を入れた。それぞれの楽曲でのアプローチがハッキリと想像しやすくなったんですよね。
加藤:太一が言ってくれた音像のクリアさも含めて、音について会話する機会が増えたと思っていて。どういう音を狙っているのか、どういう意図でこういうサウンドにしたのか、を突っ込んで訊くようになったんですよ。それはプロデューサーで入ってくださったknoakさんとのコミュニケーションも同じですし。そういった変化があったからこそ、太一が作ってくれたデモをどうやってアップデートしていくべきなのかを深く考えるようになりました。
■「別れを別れのままで終わらせたくない」(樋口)
――よく分かりました。先ほど加藤さんから「それぞれが住んでいる街と重ねて聴いてもらえたら、新たな発見がある」とも語っていただきましたが、<錆びたブリキの屋根の下の 自販機の横で 互いを気にしている>と綴られた「夢から覚めても」や<間に合わせの 理由つけて 沈む夕日 眺めてた 目眩く時の中で>と記された「moon」を筆頭に、本作は繊細な情景描写も印象的です。こうした表現が多数盛り込まれていった背景は何だとお考えですか。
樋口:周囲の状況や環境に想いを馳せるというか、身の回りの出来事に対して色んなことを考えているからかなと。周りのちょっとした変化や機微が自分の心の変化に通じているし、周りの条件に自分の気持ちも左右されていて。それを落とし込んでいった結果、自然と情景描写が多くなっていったという。
――前作『内なる惑星』はその表題が示す通り、自身の内へ内へ向かっていく一枚だったと思うんですけれど、そこで心の内に焦点を当てることができたからこそ、『Town e.p』で身の回りを描けた一面もあるのかなと。
樋口:もともと自分の頭の中にある映像を描いた上で、その情景をイメージして作詞や作曲することが多いんですが、特に「Town」に関してはセンサーが敏感になっていたと思っていて。というのも、ツアーを回ったり、ライブで色んな場所に行った経験が大きかったんですよね。通ったこともない田舎道を走っている時に、歩いているおじいちゃんを見て、「この人はここで暮らしているんだな」と思ったり、「どうやってスーパーに行って、どうやって生きているんだろう」と考えた。人と土地の関係みたいなものに思考を巡らせたことが、EPにも色濃く表れているんだと思います。

相蘇勇作(Dr)
――風景や暮らしの機微を歌っていることによって、<暖かい光 ひかり 何度でも今救ってあげるよ>(「Q」)、<ここまでくるなら 迎えにいくから 無くしたものなら 許してあげるから 怖がらないで>(「hibi」)といったど直球のパンチラインが強調されていると思うんですね。リスナーを引っ張り上げる意識が強くなってきたということも冒頭でお話いただきましたが、なぜそうした意識変化が起こったのでしょう。
樋口:活動を始めた頃は僕らの楽曲を聴いてくださる方も少なかったので、自分たちのために曲を作っている感覚だったんですけど、次第にリスナーの皆さんを意識するようになったんです。それこそ各地を巡る中で、自分たちの曲を聴いている人の顔や表情をハッキリと見ることができたのも良かった。僕らの音楽を頼りにしながら頑張っている人がいる事実は普通じゃないですし、であるならば、受け取ってくれる人のことをおろそかにしちゃだめだと思って。直接会話できるわけじゃないからこそ、受け取ってくれる人のことをきちんと考えて、もっと大切にしていきたいと思ったんですよ。
――他者との関係や相手を想うという観点で言うと、「Town」には<あのまま手を伸ばせば届いたかな でもこれでよかったから あなたが素敵なこと わかってて欲しい>というリリックが刻まれていて。別れを単に悲しみだけで終わらすのではなく、相手の幸せを祈ることによってポジティブへ変換しているのが素敵だと感じているんですが、そうした歌詞を綴ることができるのはなぜなんですか。
樋口:僕は映画が好きなんですけど、やっぱりハッピーエンドが好きなんですよね。もちろん、別れを一緒に悲しんでくれる優しさもあるとおもうんですけど、別れという変化を前向きに捉えられたら良いんじゃないかなと。別れを別れのままで終わらせたくないし、別れは新しい物語のスタートだと捉えているんです。
――過去のツアーが様々な変化のキッカケになってきたともお話いただきましたが、11月1日(土)福岡・OP’sより『goethe 2nd Live Tour』がスタートします。2024年11月の『goethe 1st live Tour』以来、皆さんにとって2度目の全国ツアーとなりますが、どのような旅路にしていきたいですか。
永江:1週間くらい余韻が続くようなライブにしたいですね。とにかくみんなが楽しんでくれて、それぞれの記憶に残ったら嬉しいです。
加藤:僕たち1人1人の立ち振る舞いや内容を含め、ライブが終わった後、「今日来て良かった」「明日からまた頑張ろう」と感じてもらえる1日にしたいと思っていて。今回は『Town e.p』だけじゃなく、『内なる惑星』も含めたボリューミーなライブになりますし、幅広い曲がある分、色んな楽しみ方ができるんじゃないかなと。
――内省的な『内なる惑星』と外へ広がっていく『Town e.p』という対照的な2枚が、どのように交わっていくのかも楽しみです。
相蘇:そうですね。2つのEPがあることでガラリと雰囲気も変わると思いますし、久々に会いにいける場所もあるんで。みんなの表情を見て色んな刺激を受けながら、最後までツアーを走り切りたいです。
樋口:みんなが言ってくれたこともそうですし、僕らはこの1年、バンドサウンドに重きを置いてというか、ライブでどうやって楽曲を表現していくかにこだわってきたんですよ。だからこそ、そういうライブならではの表現にも注目してもらえたら嬉しいですね。

取材・文=横堀つばさ 撮影=大橋祐希
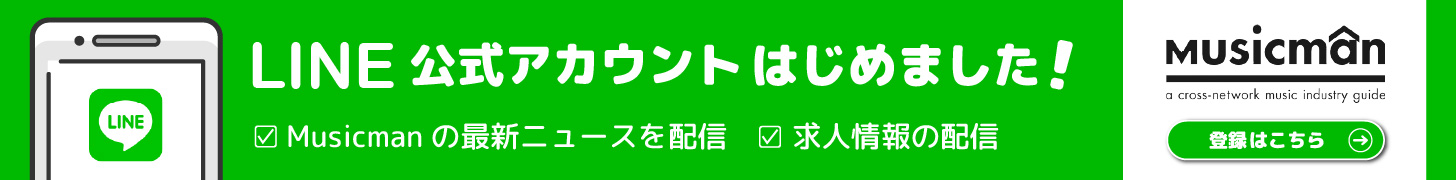
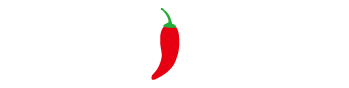
広告・取材掲載