AIがアルバムになる日「AIが音楽を変える日」連載第7回
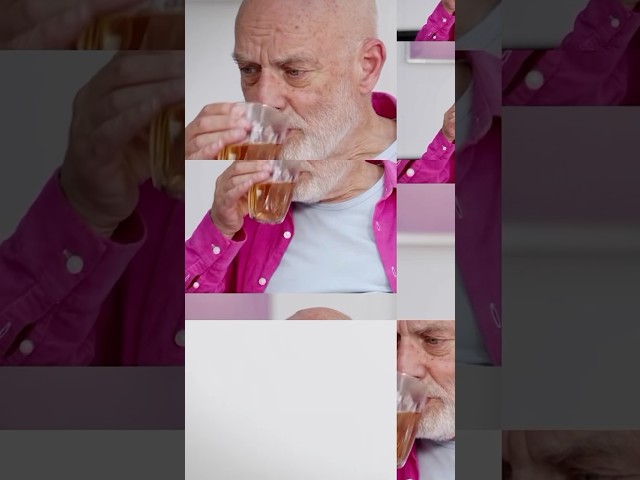
ブライアン・イーノはドキュメンタリーが嫌いだ。「観ているとイライラする」という。どんな出来のよいものでも「たったひとつの年代記的な道を辿り、全てがそこに流れ込む」から、その人物の興味深い点がほとんど削ぎ落とされてしまうのが嫌なのだそうだ。だから彼はこれまで、ドキュメンタリーを撮らせてくれという依頼は全て断ってきた。
ドキュメンタリー小説を書いてきた側の私としても、この気持ちはよく分かる。「この人を描きたい」という衝動を与える人物とは、経歴を追うだけでは捉えきれない多面的な人間だ。しかし、映画や小説には必ず一つの視点と流れが存在するので、ドキュメンタリーにしたい人物ほど、常に描写されない側面が出来てしまう。
ブライアン・イーノのドキュメンタリーを撮りたかった者は少なくないだろう。70年代のグラム・ロックのパイオニア。環境音楽、アンビエント・ミュージックの発明者のひとり。ウィンドウズ95の起動音の制作者。U2やコールドプレイのような超人気バンドをプロデュースした凄腕の音楽業界人。自身の肩書を「ノン・ミュージシャン」にする変人ぶり等々、彼は間違いなく面白くなる素材だ。
そんな彼の心を射止めたのは人間だったのか、AIだったのか。今年1月に開かれたサンダンス映画祭で映画『Eno』が公開されたが、それはAIによって生成された複数のヴァージョンを持つドキュメンタリーだった。
ゲイリー・ハストウィット監督はイーノから500時間の素材をもらうと、それを“生成アーティスト”(そんな職種がもうあるらしい)のブレンダン・ドーズに提供。ドーズはAIにその膨大な素材を学習させ、5,200京ものドキュメンタリーのパターンを生成したという。
そこから6つのヴァージョンが監督によって選択され、公開された。映画祭で観た記者は「単にランダムに並べただけではないか?」と訝って鑑賞したが、話の流れに破綻は無かったという。記者の予想では大枠の部分は監督が固めて、インサートされる素材でヴァリエーションを出したのではないか、ということだった。
ストーリーであれ音楽であれ、生成型AIが新しい作品を生み出せるのか、というのが昨今の話題だった。だが、このように一つの作品が、AIと結びついて様々なヴァリエーションを持つという道筋もある訳だ。
ゲームで見かけるマルチ・エンディングとも違う、ひとつのヴァージョンでは伝えきれない何かを表現するためのAI、つまりAI自体が表現形式となっている世界。こうしたものを私も3年ほど前、夢想して書いたことがある。
「おそらく“強いAI”とBUI(ブレイン・ユーザー・インターフェース)で育った未来の世代は『録音した、何度聴いてもどこも変わらない曲』に退屈してしまうだろう。彼らにとって、聴く度に演奏と歌声を微妙に変え、様々な表情を見せる楽曲こそ、シングルやアルバムとして聴くべき作品になっているのかもしれない」
これは拙著『音楽が未来を連れてくる』(DUブックス)の終章で、30年後の未来を予想して書いたものだが、この原稿を書いたわずか2年後にChatGPTが公開され、瞬く間に生成型AIが世界を席巻するとは夢にも思っていなかった。本稿を書いているひと月前にはさらに、AIの力で「聴く度に演奏と歌声を微妙に変え、様々な表情を見せる楽曲」も実際に販売された。
おそらく音楽の産業史に残るその曲を書いたのはディスクロージャー。ロンドン近郊出身のローレンス兄弟によるユニットだ。サム・スミスをヴォーカルに迎えた「ラッチ」で2014年、世界的にブレイクした彼らは最近、アルバムの新作をリリースした。その中の1曲「Simply Won’t Do」を、ブロンズ(Bronze)という名の音楽生成AIでリミックスした。ブロンズが生成したリミックスの数は実に千曲で、人間のDJには不可能な数だ。
「ブロンズはロジック(Appleの音楽制作ソフト)みたいなもので、デジタル・ワークステーションだ。でもロジックには出来ないことがたくさんできる。ブロンズとロジックを組み合わせて使うのはとても強力だ」とディスクロージャーのガイ・ローレンスは語る。
この1,000曲はNFTになっていて、それぞれ20ドルで販売しているが、購入しなくても下記で試聴できる。聴き比べると、なかなかのクオリティで曲ごとに差異が付いていると気づくだろう。そして私がかつて書いた、聴く度に様相を変える曲を楽しむ時代がすぐそこまで来ていると分かるはずだ。
「NFTで音楽を売るのは今更ではないか」と感じる方もいるだろう。私もそう思う。しかし、「楽曲AI」を個別に売れる配信プラットフォームはまだ存在しない。いずれ、そうしたプラットフォームが誕生するのではないか。それは音楽産業にとって福音となる可能性がある。人びとは楽曲AIをまとめた「AIアルバム」をかつてのCDのように都度購入するようになるかもしれないからだ。
先のディスクロージャーの作品は1,000個のヴァージョンそれぞれに独自のジャケットが備わっている。個別の波形に合わせて生成されたものだ。ジャケットというのは画像だが、これが映像になったらどうなるだろう。Appleのヴィジョン・プロのようなスマートグラスが普及した頃には、観る度に様相を変えるインスタレーションのような音楽ビデオが出てくるのではないだろうか。
人類は、イヤホンから何度聴いても同じ曲が流れ、スマホの小さな画面で何度も同じ音楽ビデオが流れる今のアート・フォームにもう飽きている気がする。音楽アルバムはいずれチームラボボーダレスが創るインスタレーションのミュージアムを仮想空間で作ったような、万人の楽しめるアトラクションみたいなポップ・アートになるのかもしれない。それは現在の技術でもぎりぎり出来なくはない。
いつ、そんな時代が来るのか? 30年後と書いたら3年後だった轍を踏まないためにそれは記さないが、今の音楽ビデオもMTVが登場した1981年には最新の技術を駆使したアート・フォームだった。少なくとも楽しみに待っていれば、新しい始まりの瞬間を見逃すことは無いだろう。
※「AIが音楽を変える日」は現在『新潮』(3月7日に最新号発売)にて連載中。Musicmanでは1月遅れで同連載を掲載していきます。

『新潮』2024年4月号(新潮社)
著者プロフィール
 榎本幹朗(えのもと・みきろう)
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。現在『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載中。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載