国立音楽大学、演奏時における空気流出に関する研究結果を発表

国立音楽大学は9月16日、三浦雅展准教授(音響学)による声楽および管楽器演奏時における空気流出に関する実験結果を発表した。
三浦雅展准教授は、国立音楽大学の協力の下、吹鳴楽器および歌唱時における空気流の計測を行なった。吹鳴や歌唱によって演奏する楽器において、演奏時の音響放射特性や音響信号の特徴を調査した研究が多数見られるが、演奏時における空気の流れを測定した研究はこれまであまりみられなかったため、吹奏楽器における演奏時の空気の流れを測定。演奏時の音響特性ではなく、空気流出に着目した点がこれまでにない新しい試みとなった。
演奏時における空気の流れを知ることで、楽器演奏の様相を詳しく知ることができると考えられる。例えば、楽器演奏時における吹鳴行為と演奏音の関係がわかることで、演奏者が行なう吹鳴制御の指針を作ることが期待できるとしている。
調査の結果、以下の点が明らかになった。
- 全般的に金管楽器の空気流出はベル部からに限られており、その量も限定的である。
- 木管楽器の場合は、楽器のベルやトーンホールからの流出があり、金管楽器よりも多く観測された。
- 声楽(テノール)の場合は、発話の内容によって空気の量や方角が異なる。
なお、詳細な実験結果については、国立音楽大学公式サイトの「ニュース」ページにて公表されている。
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
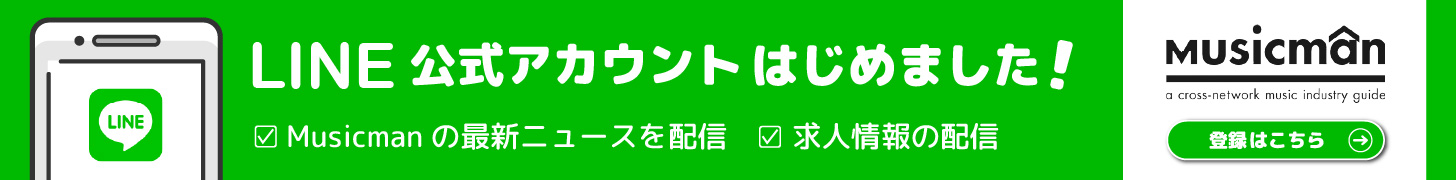
広告・取材掲載